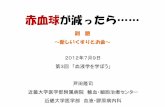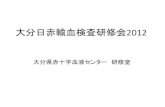血液細胞の生成 骨髄 末梢血muraka-h/class/2017/3-GF.pdf骨髄 末梢血 白血球 赤血球 多能性 幹細胞 血液細胞の生成 すべての血液細胞 は一種類の共通の
松山赤十字病院 モーニングレクチャー...
Transcript of 松山赤十字病院 モーニングレクチャー...
消化管出血とは?
消化管からの出血は主に吐血・下血などの症候として現れる。
①吐血:肉眼的に確認しうる血液成分を嘔吐すること。 一般に出血源はTreiz靭帯より口側に存在する。 喀血との鑑別が必要。
②下血:黒色便を排泄する現象。
60-100ml以上の出血をきたすと便が黒色となる。 一般に出血源は上部消化管に存在するが、下部消化管出血でも腸管内に長く停滞すると黒色便がみられる。 服用薬剤や摂取した食物について問診が必要。 (鉄剤など)
消化管出血とは?
消化管からの出血は主に吐血・下血などの症候として現れる。
③血便:赤色あるいは暗赤色の便。 一般に出血源は下部消化管に存在するが、上部消化管
からの出血であっても急速な大量出血により血便を呈することがある。
下血はタール様便、melenaと同義とされる。 肛門からの赤色血液の排泄を意味する血便とは区別される。
ショックの診断
2. 小項目 ①心拍数100回/min以上
②微弱な脈拍
③爪先の毛細血管のrefilling遅延
(圧迫解除後2秒以上)
④意識障害
JCS2桁以上またはGCS10点以下
または不穏•興奮状態
⑤乏尿•無尿(0.5mL/kg/hr以下)
⑥皮膚蒼白と冷や汗または39℃以上の発熱
(感染性ショックの場合)
1. 血圧低下
◆収縮期血圧≦90mmHg
◆平時の収縮期血圧≧150mmHg
→平時より60mmHg以上の血圧下降
◆平時の収縮期血圧≦110mmHg
→平時より20mmHg以上の血圧下降
血圧低下+小項目3項目以上を満たす→ショックと診断
日本救急医学会編
ショックの診断
2. 小項目 ①心拍数100回/min以上
②微弱な脈拍
③爪先の毛細血管のrefilling遅延
(圧迫解除後2秒以上)
④意識障害
JCS2桁以上またはGCS10点以下
または不穏•興奮状態
⑤乏尿•無尿(0.5mL/kg/hr以下)
⑥皮膚蒼白と冷や汗または39℃以上の発熱
(感染性ショックの場合)
1. 血圧低下
◆収縮期血圧≦90mmHg
◆平時の収縮期血圧≧150mmHg
→平時より60mmHg以上の血圧下降
◆平時の収縮期血圧≦110mmHg
→平時より20mmHg以上の血圧下降
血圧低下+小項目3項目以上を満たす→ショックと診断
日本救急医学会編
ショックの診断
ショックの5Ps
Pallor 蒼白
Prostration 虚脱
Perspiration 冷汗
Pulselessness 脈拍触知不能
Pulmonary deficiency 呼吸不全
ショックの診断
ショック指数
ショック指数 (心拍数/収縮期血圧)
重症度 出血量
(%, 有効循環血液量に対する割合)
0.5~0.7 正常
1.0 軽症 約23(約1.0L)
1.5 中等度 約33(約1.5L)
2.0 重症 約43(約2.0L)
出血量からみたショックの重症度分類
1:バイタルサインのチェック、血管確保、 輸液、血液検査など 2:問診 3:出血量の推定(重症度診断) 4:輸血の必要性
Class Ⅰ ClassⅡ ClassⅢ ClassⅣ
出血量 (%, 有効循環血液量に
対する割合) <15 15~30 30~40 >40
出血量 (mL, 体重70kgで換算)
<750 750~1500 1500~2000 >2000
脈拍数(/分) <100 >100 >120 >140または除脈
血圧 不変 不変 低下 低下
脈圧 不変~増
加 減少 減少 減少
呼吸数(/分) 14~20 20~30 30~40 >40
意識レベル 軽い不安 不安 不安・不穏 不穏・無気力
米国外科学会編
消化管出血に関する問診のポイント
1.出血の状態
出血の状況、出血量など
2.随伴症状
腹痛、共通、発熱、悪心、嘔吐など
3.既往症
消化性潰瘍、肝疾患、直近の内視鏡検査など
4.服用している薬の内容
NSAID、抗血栓薬、ステロイド、抗菌薬など
バイタルサインからみた出血量の推定と重症度判定
バイタルサイン 出血量 重症度
著明な変動なし 500ml以下
(10%以下)
症状なし
頻脈(100/分以下)
血圧低下(100mmHg以上)
四肢冷感
750~1250ml
(15~25%)
軽症
頻脈(100~120/分)
血圧低下(80~100mmHg)
脈圧減少、冷汗、顔面蒼白、
不穏、尿量減少
1250~1750ml
(25~35%)
中等症
頻脈(120分以上)
血圧低下(80mmHg以下)
意識低下、呼吸促迫、無尿
2500ml以上
(50%以上)
重症
急性出血に対する血液製剤の使用指針(厚生労働省)
出血量 血液製剤の使用指針
①15~20% 輸液で対応し、血液製剤は使用しない
②20~50% ①に加え赤血球濃厚液を使用する
③50~100% ②に加えて等張アルブミン製剤を使用する
④100%以上
(24時間以内)
③に加えて新鮮凍結血漿や血小板濃厚液を使用する
消化管出血の頻度
上部消化管出血(70~80%)
① 胃潰瘍(30.3~42.4%) ② 十二指腸潰瘍(7.6~23.0%)
③ 急性胃粘膜病変(AGML)(約10%) ④ 食道静脈瘤破裂(約10%)
⑤ 悪性腫瘍(1.8~6.8%) ⑥ Mallory-Weiss症候群(2.1~6.4%)
小腸出血(5%)
大腸出血(20~30%)
① 虚血性大腸炎(4.0~31.9%) ② 痔核、肛門病変(4.0~25.4%)
③ 腸炎(3.3~21.9%) ④ 大腸癌(2.8~18.5%)
⑤ 大腸ポリープ(0.4~17.4%) ⑥ 潰瘍性大腸炎(3.4~12.5%)
⑦ 大腸憩室出血(1.8~7.9%)
① H.pylori菌感染
② アスピリンを含む非ステロイド性抗炎症薬
(Nonsteroidal anti-inflammatory drugs:NSAID)
・非アスピリンNSAID : 解熱鎮痛作用
・低用量アスピリン : 抗血小板作用
胃十二指腸潰瘍の2大原因
NSAIDと病態 細胞膜リン脂質
非アスピリンNSAID
アラキドン酸
COX-1
選択的COX-2阻害薬
プロスタグランジン
(以下、PG)
(可逆的競合阻害)
(不可逆的阻害)
ホスホリパーゼA2
炎症、疼痛、発熱を仲介
COX-2
阻害
胃、十二指腸粘膜の保護
PG
アスピリン
トロンボキサン
(血管収縮、血小板凝固作用)
出血性胃十二指腸潰瘍(508例) NSAIDとH.pylori
NSAID(+)
H.pylori(+)
98例(19.3%)
H.pylori(+)
327例(64.4%) NSAID(-)
H.pylori(+)
229例(45.1%)
NSAID(+)
H.pylori(-)
110例(21.6%)
NSAID(-)
H.pylori(-)
71例(14.0%)
NSAID(+)
208例(40.9%)
<対象・方法>
2002年1月から2009年12月までの8年間に当センターで内視鏡的止血術を施行した出血性胃十二指腸潰瘍508例を対象とし、NSAID使用歴の有無より、NSAID
群と非NSAID群の2群に分類した。さらにNSAIDをアスピリンと非アスピリンNSAIDに分類し、その使用歴によりNSAID群をアスピリン群(アスピリン使用例)、併用群(アスピリンと非アスピリンNSAID併用例)、非アスピリンNSAID群(非アスピリンNSAID使用例)に分類した。各群ごとにその臨床像と内視鏡像を遡及的に比較検討した。 川崎啓祐, 蔵原晃一, 他:消化器内科51, 2010.
アスピリンとNSAID(208例243薬剤)の種類
アスピリン
83例(34%)
ロキソプロフェン
51例(21%)
ジクロフェナク37例
(15%)
ケトプロフェン
11例(4%)
ロルノキシカム
9例(4%)
エトドラク 7例(3%)
メロキシカム 5例(2%)
インドメタシン
5例(2%)
セレコキシブ 2例(1%)
その他33例(14%)
555人に1人予防
低用量アスピリン療法での
イベント発症予防と消化管出血の頻度
-24文献(66,000例)のメタ解析結果-
イベント発症予防効果(number needed to treat per year)
心筋梗塞の一次予防 SALT study . Lancet 1991
脳卒中の二次予防 US Physicians Health Study.
NEJM 1989
106人に1人予防
消化管出血発症頻度(number needed to harm per year)
消化管出血 248人に1人発症
0 200 400 600
Derry et al. BMJ,32,1183-1187,2000.
出血性胃十二指腸潰瘍自験508例のまとめ
・ 出血性胃十二指腸潰瘍508例中、アスピリン/非アスピリンNSAID併用例 は18例(3.5%)であった。
・ アスピリン/非アスピリンNSAID併用群はアスピリン群、非アスピリン NSAID群、非NSAID群と比較して来院時Hb値、血清H.pylori IgG抗体陽 性率が低値であった。
・ NSAID使用例、特にアスピリン使用例は増加傾向にあり、それに伴い
アスピリン/非アスピリンNSAID併用例も増加傾向にあり、今後更なる
検討を要すると考えた。
川崎啓祐, 蔵原晃一, 他:消化器内科51, 2010.
出血性胃十二指腸潰瘍に対する内視鏡的止血法
薬剤散布法
局注法
(安価で簡便)
機械的止血法
(組織障害が少ない)
組織凝固法
(手技的に容易)
トロンビン
エタノール
純エタノール局注
HSE局注
クリップ
結紮法(EVL)
ヒータープローブ
バイポーラプローブ
APC
内視鏡的止血術
血管収縮、フィブリノイド変性と
周囲組織の膨化による血栓形成。
露出血管周囲に1-2mlずつ数カ所に局注。
(総量10-20mlまで)
組織障害は比較的弱いが総量が増えると潰瘍が大型化する。
HSE Hypertonic saline and epinephrine
( 10%NaCl 20ml + ボスミン1-2ml ) 局注法
APC(argon plasma coagulation)法
非接触型。
アルゴンガス放出と放電による組織の熱凝固。
深部組織への凝固作用が少なく安全。
径の太い露出血管に対して効果不十分。
NSAID使用あり HP陽性
NSAIDの中止
NSAIDの投与継続 1)PPI
2)PG製剤(ミソプロストール)
止血後の潰瘍治療のフローチャート
除菌
NSAID使用なし
HP陽性
HP陰性 除菌によらない治療
(PPI、H2RA)
出血性胃十二指腸潰瘍の発症予防のために
・抗凝固療法、線溶療法の開始前には上部消化管内視鏡検査と
便潜血検査を施行する。
・胃十二指腸潰瘍の既往のある患者には、H. pylori除菌療法を
検討する。
・ハイリスク症例にNSAIDを投与する際には
PPI の併用投与を考慮する。
NSAID潰瘍のハイリスク要因
1. 高用量・複数のNSAIDの使用
2. 潰瘍の既往
3. ステロイドの併用
4. 抗血小板薬・抗凝固薬の併用
5. H.pyroliの合併
6. 75歳以上の高齢者
7. 全身疾患(心、肺、肝疾患など)の合併
消化管出血の頻度
上部消化管出血(70~80%)
① 胃潰瘍(30.3~42.4%) ② 十二指腸潰瘍(7.6~23.0%)
③ 急性胃粘膜病変(AGML)(約10%) ④ 食道静脈瘤破裂(約10%)
⑤ 悪性腫瘍(1.8~6.8%) ⑥ Mallory-Weiss症候群(2.1~6.4%)
小腸出血(5%)
大腸出血(20~30%)
① 虚血性大腸炎(4.0~31.9%) ② 痔核、肛門病変(4.0~25.4%)
③ 腸炎(3.3~21.9%) ④ 大腸癌(2.8~18.5%)
⑤ 大腸ポリープ(0.4~17.4%) ⑥ 潰瘍性大腸炎(3.4~12.5%)
⑦ 大腸憩室出血(1.8~7.9%)
大腸憩室出血
26例(40.6%)
出血性直腸潰瘍
18例(28.1%)
大腸毛細血管拡張症
15例(23.4%)
その他
5例(7.8%)
内視鏡的止血術を施行した64例の原因疾患
【対象と方法】 2004年8月から2010年3月までの最近5年8ヶ月間に
当センターで大腸出血と診断し、内視鏡的止血術を施行した症例64例を対象とし、その臨床像や出血原因、止血方法などについて遡及的に検討した。
※大腸癌 2例
juvenile polyp、放射線性腸炎
原因不明の潰瘍 各1例
阿部光市, 蔵原晃一, 川崎啓祐, 他:松山赤十字病院医学雑誌35, 2010.
臨床像の比較
大腸憩室出血 26例
出血性 直腸潰瘍
18例
大腸 毛細血管拡張症
15例 p-value
平均年齢 70.0才 74.1才 76.4才 N.S
性別(M/F) 23/3 7/11 8/7 p<0.05
5日以上の臥床 2例(7.7%) 15例(83.3%) 3例(20.0%) p<0.05
使用薬剤
①抗血栓剤 8例(30.8%) 8例(44.4%) 9例(60.0%) N.S
②NSAID 8例(30.8%) 11例(61.1%) 5例(33.3%) p<0.01
検査時Hb値(g/dl) 10.0 9.04 7.35 p<0.01
阿部光市, 蔵原晃一, 川崎啓祐, 他:松山赤十字病院医学雑誌35, 2010.