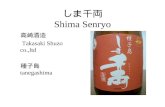欧州・スウェーデンにおける若者参加 (2014年.両角達平)
-
Upload
tatsuhei-morozumi -
Category
Education
-
view
55 -
download
3
Transcript of 欧州・スウェーデンにおける若者参加 (2014年.両角達平)
1
静岡県立大学国際関係学部
国際言語文化学科アジア文化コース
2013 年度卒業論文
欧州・スウェーデンにおける若者参加
スウェーデンのあるユースセンターにおける取り組み
静岡県立大学国際関係学部国際言語文化学科アジアコース
両角達平
2
目次
⽬次_______________________________________________________________ 2
はじめに___________________________________________________________ 3
本稿の⽬的と課題 ______________________________________________________________ 5 第一章社会的排除層としての若者の浮上と参加の必要性 __________________________ 6
社会的排除層としての若者の浮上 ______________________________________________ 6 第二章若者の参加のあり方とその方法 _________________________________________ 9
ロジャー・ハート参加の梯子の批判検討 ________________________________________ 9 若者の参加の方向性 ________________________________________________________ 11
影響⼒と参加 ________________________________________________________________ 16 第三章ケーススタディ:ストックホルムのユースセンターの事例 ________________ 18
調査方法 __________________________________________________________________ 18 施設の概要 ________________________________________________________________ 20
終章 スウェーデンにおける若者参加の認識と課題 ______________________________ 37 現場における若者参加 ______________________________________________________ 37 スウェーデンの若者の「実際の」社会への影響力とその課題 ____________________ 39
結論______________________________________________________________ 43
おわりに ____________________________________________________________________ 44 スウェーデンと日本を比較するということ ____________________________________ 44 日本への示唆 ______________________________________________________________ 45
謝辞 ________________________________________________________________________ 48
参考⽂献__________________________________________________________ 50
3
はじめに
2009 年筆者は、若者の社会参加を活性化させることを目的とした YEC(若者エンパワメン
ト委員会)という学生 NPO を本大学、津富宏教授とともに立ち上げた。本団体は、大学生が
構成員のほとんどを占めるので、「若者による若者のため」を重要なコンセプトに添えた。
啓発と YEC 自身の勉強会を目的とし、講師を招いたワークショップを開催すると同時に、若
者(主に中高生)を対象にした事業を行なった。本事業では、中高生の実現したいこと(バ
ンドやダンスイベントなどから社会的なプロジェクトまで様々)を大学生とともに、または
社会人からのサポートも受けながら実現していくというものである。その過程で筆者は時
に、同世代の若者が若者を助けることの困難さに直面しつつも若者のエンパワメントや・社
会参加の可能性と重要性を実感してきた。同時にいくつかの疑問が浮かんできた。彼ら彼女
らの社会参加を促進するために以下にサポートをすればよいのか。 善の方法は何か。そも
そも若者の社会参加とは何か。
2010 年 5 月、ある NPO 法人が主催したスウェーデン・スタディツアーに参加した。この
スタディツアーでは、スウェーデンの教育・若者政策に学び日本に活かすということを目的
としており、教育・若者政策に関わる省庁や学校、余暇活動施設(ユースセンター)、学校
選挙、全国若者会議、全国生徒会、などを訪問しインタビューを行なってきた。同スタディ
ツアー中に筆者は、ストックホルム中央駅周辺にてアンケート調査の実施をした。
4
アンケートの質問項目は静岡の街中でその2か月前ほどに実施したアンケート調査と同内容
のものとすることで、単純ではあるが比較可能にし、日本(静岡)とスウェーデン(ストッ
クホルム)の若者間での意識の差異を考察することを目的とした。同調査で明らかになった
のは、「あなたは自分が社会を変えることができると思いますか?」という質問に対して、
スウェーデンの若者は 65%が、日本の若者は 24%が「はい」と答えた。1
どちらの調査とも無差別に路上を声かけをした若者たった 100 人の返答を採用したのみで
あるので、およそ学術的・客観的な方法で実施されたとは言い難いが、それでもこの結果
は、スタディツアーにて様々な組織を見てきた筆者にとっては示唆に富むものであった。
日本青少年研究所〔2009〕
実際、似たような調査は既に実施されており、日本青少年研究所(2009)の実施した調
査によると「私の参加により変えてほしい社会現象が少し変えられるかもしれない」という
質問に対して約7割の日本の高校生が否定しているのに対して、「全くそう思う」「まあそう
思う」と答えた高校生がアメリカでは 69,8%、中国では62,7%そして韓国では 68,4%で
あった。この調査にはスウェーデンは含まれていないが、若者の社会に対する自己認識が見
て取れる。ウーッドヘッド(Woodhead,2002)が、日本社会やその他のアジアの文化では、
人権を基盤とした自律した個人という概念を翻訳することの困難さを指摘しているように、
日本と西欧では社会に対する意識にある程度の差異がある。しかし、日本青少年研究所の調
査が示唆深いのは、若者の意識の相違が同じアジア圏内である中国、韓国との間ににあると
いうことである。これは西欧文化とアジア文化の相違がそれぞれの若者の意識の相違の原因
1 当該団体ホームページよりダウンロード http://youth-empowerment.jimdo.com/ダウンロード
/yec 若者アンケート
5
とはならないことを意味付けているとといっても言い過ぎではないだろう。
ではなぜ、日本の若者の社会に対する意識がここまで低く、西欧特にスウェーデンでは高
いのであろうか。スタディツアーに参加後、著者は、スウェーデンには若者が「民主主義社
会」へと参加することのできる機会が多様かつ豊富であり、学校や非政府組織だけでなく行
政機関ですらそれらの必要性を認識し、制度的にかつ包括的に若者を支えているのだろうと
憶測した。さらには、社会参加の概念そのものと若者の社会参加にむけた取り組みについて
も大きな違いがあるのではないかという問題意識も相まりそれらを本論文のテーマとするこ
ととした。
本稿の目的と課題
本論文の目的を以下のように掲げる。
まず本稿では若者の社会参加の必要性と重要性について現代の若者が社会的弱者・社
会的排除の被害者に転落しているという状況認識から論じる。
次に子ども・若者の社会参加とは何か、代表的であるロジャー・ハートの参加の梯子
の枠組みについて批判検討をし、さらに児童の権利条約、EU 若者政策、スウェーデン
若者政策、において参加がどのように扱われているのかについて考察する。 後に、
スウェーデン首都ストックホルム南部に位置するあるユースセンターを事例にケース
スタディを用いて、ユースワーカーと利用者の若者のインタビューから、現場におい
て若者の参加がどのようにして促されているのか、それにまつわる問題などについて
論じる。
6
第一章 社会的排除層としての若者の浮上と参加の必要性
社会的排除層としての若者の浮上
近年、「若者」という言葉をめぐって様々な議論が起きている。その先がけは、ニート・
ひきこもりの若者が社会問題として浮上したことに端を発するだろう。若者の就職難、失業
率の上昇、フリーターの増加などの若者の雇用の不安定化により出現した、これらの層は時
に「だらしのない若者」として若者叩きにあいつつも、いよいよ問題化し社会的に認知さ
れ、ようやく国が重い腰を上げて動き出したのは 2009 年に国が子ども若者育成支援推進法
を制定した頃であろう。 も現場レベルでは 2000 年前後には様々な取り組みが展開されて
いた。障害者や女性がかつて(あるいは現在も)社会的に力が発揮できず、地位向上のため
に奮闘してきた歴史があるように今や、若者という世代がその社会的弱者層となってしまっ
たのである。しかし、同法による施策を始め様々な民間団体等による取り組みは、就労支援
を重視したものがほとんどであり、宮本(2007)2が「しかしそれだけを進めることを許すこ
とになれば、景気がよくなったら若者問題から一気に手を引いてしまうだろうと思うので
す」と危惧するように現在の部分的な取り組みは多様で複雑化した若者を取り巻く問題を解
決する持続可能な施策と言えるのか筆者は疑問を感じている。若者を取り巻く社会状況は、
学校教育機関の長期化、消費社会の拡大による若者の社会関心の希薄化、家族や家族外の社
会的ネットワークの弱体化、さらには若年人口の減少による若者世代の影響力の低下と社会
的地位の喪失3、などという多次元の諸問題が複雑に絡み合っているからである。
それでは『社会的排除層として若者が浮上した』とはどういうことだろうか。そもそも社
会的排除という言葉は、戦後復興と福祉国家の諸制度が整備された 1970 年代のフランスの
中で、その中でも排除された、障害を持つ人々等成長から取り残された層を社会へ参入させ
ることの必要性を当時の政策担当者らが訴えたことから生まれたとされている。(岩
田,2008)この言葉が再び注目されるようになったのは 1980 年代の欧州における若年失業者
問題であった。ここで岩田は EU やイギリスの「ソーシャル・エクスクルージョン・ユニッ
ト」という特別機関の文章を引用した上で、社会的排除を
● それが行なわれることが普通であるとか望ましいとか考えられるような社会の主活
動への「参加」の欠如を、ストレートに表現したもの
● 社会関係が危うくなったり、ときには関係から切断されているということ
と端的に表現している。貧困などではその生活の「資源」の不足を中心概念にして把握して
いるのに対して、社会的排除は「関係」の不足に着目をする、という補助線引きを直後でし
ている。つまり若者が社会的排除層として認識されるようになったということは、若者を取
り巻く社会状況に対応する形で、主たる影響を被った若者の社会的地位が様々な点から低下
2宮本みち子, 2007, 格差社会と若者の未来 3同上
7
したということである。
同じような認識は 2001 年に欧州議会によって提出された欧州若者白書 2001 に4置いても
指摘されている。1970 年代以降のポスト工業化における欧州の若者を取り巻く社会経済状
況、労働市場、少子高齢化による人口構造の変化を背景に、若者自身の高学歴化、若年労働
市場の流動化、消費市場の拡大と IT 化の進行による若者の社会的関心の希薄化が急速的に
進行した。これらの欧州の共通の課題を指摘した同白書には以下のような記述がある。
ともかく、若きヨーロッパ人には言いたいことがたくさんあるはずだ。結局のとこ
ろ、彼らこそ、経済的変化、人口のアンバランス、グローバリゼーション、文化的
多様性によって、主たる影響を被っている、まさにその人たちである。私たちは、
新たな不安定性が現れる時代にあって、若者が新たな社会関係のかたち、すなわち
連帯を表明する新たな方法や、異質性と対応し、そのうちに豊かさを見いだす新た
な方法を創造することを期待する。
より複雑化する社会的・経済的状況にも関わらず、十分に適応する用意がある若者
を、私たち社会の「一員」とすることで、この変化の過程を促進することは、各国
ヨーロッパレベルの政治家の責任である(欧州若者白書,2001)
ここに欧州の若者の状況認識が端的に現れている。現代を「物語化できない人生」と大澤
(2011)5が表現したように、かつてのように将来設計がしづらい先行きが「不透明」になっ
ている現代において、 もその被害を被っているのは今を、そして次代を生きる若者である
からこそ、若者の包摂が叫ばれている。この白書を皮切りにヨーロッパでは EU の枠組みと
して、こういった状況認識に基づいた上で若者政策が形作られていくこととなったが、これ
については後の章にて触れることとする。
それでは具体的に、どのような指標に照らして社会的排除は認識されているのだろうか。
岩田は、タニア、パーシーそして EU の分類を以下のように提示している。
● タニア・バーカード:消費活動・生産活動・政治的参加・社会的交流
● パーシー・スミス:経済的側面・社会的側面・政治的側面・近隣・個人的側面・空
間的側面・集団的側面・
● EU:経済・教育・雇用・医療・住宅・社会参加
これらの指標区分に照らして明らかになるのは、社会的排除は、経済的生産・消費活動な
どのみならず、社会的交流、政治的・社会的参加などもその指標として位置づけられている
4Council of Europe, 2001 5大澤真幸, 2011, 「正義」を考える
8
ことである。もちろんこれらの要素が複雑に絡み合って表出するものであるが、「参加」の
欠如が社会的交流、政治的社会的側面に置いても生じているということは見過ごしてはなら
ない点である。
さらにパーシーは、「社会的排除とは社会的資本(ソーシャル・キャピタル)の不足」と
して、その社会的資本を以下のように整理整理している。
①地域ネットワークの存在②このネットワークへの市民の参加③地域アイデンティ
ティや連帯感④他のメンバーとの間の相互扶助や信頼の規範の存在
つまり、家族や地域などを含めた他者との相互扶助を通じて「いつでも相談できる人」や
人的な資本に対してアクセスできるようにするということである。若者間において進行して
いる「格差」は、社会関係資本の有無も意味しており、より社会関係資本の多い若者は、困
難な状況に陥ったとしても相談をし助けを得られるのであり、逆もまた然りである。
それでは、若者の社会関係資本の構築はいかにして保障され得るのであろうか。筆者は、
ユースワークにその可能性を見いだす。ユースワークは、「学校外でのインフォーマルな教
育活動を通じて、楽しさや、挑戦、学習、成長を伴いながら、若者が、自分自身や他者、社
会を学ぶことを支援する取り組み」として NationalYouthAgencyによって定義されてい
る6ように、学校教育は教科教育を重視するのに対して、ユースワークは学外において様々
な活動を通じて実施される。また平塚は、平等な参加を強く志向する社会関係資本づくりの
必要性について言及する中で「とりわけ実践面で示唆的なのは、近年 EU 圏で展開しつつあ
るユースワーク(YouthWork)実践の、不利な立場にある若者たちの社会関係資本の形成に焦
点化した取り組みである」7として、ユースワークが社会関係資本構築に実践的役割を果た
す取り組みとして紹介した。
以下に、ここまでの要点をまとめる。
● 若者をめぐる社会の状況が脱工業化を経た先進国を中心に急進し、今や若者は社会
的排除を被っている層として表出
● 社会的排除とはある主たる社会への参加及び、社会関係資本の「欠如」が起きてい
る状態であること
● 物質的・経済的な支援のみならず、社会参加を社会関係資本の構築を含んだものと
して認識しそれに基づいた若者政策・施策としてユースワークが重要な役割を担う
ことができる
6 NPO 法人 Rights, 2011, 英国スタディツアー報告書 7平塚眞樹, 移行システム分解過程における脳欲観の転換と社会関係資本, 2006
9
こういった状況認識に基づいた上で、それではいったいどのようにして、社会関係資本構
築としての若者政策・施策、ユースワークが有効なのであろうか。再び「参加」という言葉
に立ち戻り、若者の社会関係資本構築のためにいかにして、若者は参加すべきなのか、次節
で批判検討する。
第二章 若者の参加のあり方とその方法
ロジャー・ハート参加の梯子の批判検討
”子どもの参加の梯子”は、アンスティン(Arnestin,1969)の「市民参加の八段の梯子」
を原型にロジャー・ハート(R.Hart,1997)によって開発・提唱され、子どもの参加論の代表
的な枠組みとして今日まで様々なレベルの現場で活用されてきた。彼によると梯子の 初の
三段は「操り」「お飾り」「形だけ」の非参加の状態としている。4 段目以上を参加の状態で
あるとし 4 段目を「与えられた役割を認識した上での参加」5 段目を「大人主導で子どもの
意見提供ある参加」6 段目を「大人主導で意思決定に子どもも参加」7 段目を子ども主導の
活動」そして 終段階を「子ども主導の活動に大人も巻き込む」と分類している。ハート
は、この 終段階は、子どもと大人の間で意思決定と協働をし責任を共有する機会であると
し、互いの人生の経験から学び互いの情報を入手できるように大人が協力的で助言者の役割
を果たしているときのみ、そのような機会が実現するとしている。この段階において彼は特
に大人と子どもの間で責任を分かち合うことが、子ども主導の参加を実現していくには重要
な点であることを強調している。ハートのみならず、1990 年に施行された「子どもの権利
および福祉に関するアフリカ憲章」においても、子どもの「権利」と「責任」の両方を強調
しており、地域コミュニティの子どもに対する共同的な責任にも同程度の比重を置いている
(Woodhead,2002)。事実、第一条項においては「子どもの権利」とではなく、「権利と義
10
務」という表現を用いている。これらの記述からも参加には「責任」と「権力」の分譲が表
裏一体であることが明らかである。
一方でハートの参加の梯子に寄せられる批判もある。参加の梯子を枠組みとして利用する
際に、ロバーツ(Roberts,2003)によると、 高位の参加の段階に達していないという恐れ
によって、行動の機能不全に陥るという危険性が指摘されている。また、一段ずつ参加のス
テップを進む代わりに 終段階へ飛びたいという動機をもたらす可能性を指摘している。こ
れは、参加のステップを時系列に登るべきだということを意味しているわけではなく、子ど
もの興味と能力によってどの段階の桟にそれぞれの参加型プロジェクトを配置するかはむし
ろ個々の判断に委ねられていることを意味している。
また、ミカエル(Gallagher,Michael,2008)はフーコー(Foucault)を引用してハートの
参加の梯子を批判している。
権力は、それ自体が循環し、むしろ連鎖の形体をとる中でのみ機能するものとして分
析されるべきである。それは決してあらゆる所、誰かの手に局在化されてはならず、商品
及び富の一部として占有されてはならない。権力は網状の組織によって用いられ、行使さ
れなければならない。(Foucault,1980b:98)
ミカエルの分析によると、この理論は大人・子ども(もしくはその両方)の権力の共有度
合いに応じた子どもの参加を分類するハートによる既存の理論と対比されうると指摘してい
る。しかし一方で、多くの実践家は、それぞれの実践でハートのモデルを用いて認識を助け
たり、ある種の非参加を駆除するなどしてハートのモデルをもっとも利便性の高いものと認
識しているという主張もある。
以上がハートの参加の梯子をめぐる議論であるが、要約すると、ハートの枠組みは大人主
導の偽りの子どもの参加から、子どもによる意思決定と責任を共有した「真の参加」へのガ
イドラインを示しているが、序列化による参加のそもそもの機能不全に陥る可能性や、興味
や能力に応じて参加の段階は柔軟に配置されうる点に配慮をし、権力は大人と子どもという
関係のみならず、多様な網状組織を循環するようにして行使されなければならない、とまと
められよう。
参加の梯子を中心とした議論では、梯子を登るようにして、偽りの参加から真の参加への
道筋が開ける。しかしでは、参加の方向性という点ではではどうだろうか。いったい「何
に」参加するのか、参加するその先は何なのかについて、児童の権利条約、EU 若者政策、
スウェーデン若者政策から探っていく。
11
若者の参加の方向性
児童の権利条約
子どもの参加は、1985 年の世界青年年を発端に同年代にその必要性が世界各地で主張さ
れ、1989 年に実施された国連総会で子どもの権利条約が採択された。日本では 1994 年に批
准をした。子どもの権利条約は、『保護される権利」「生存の権利」「発達の権利」そして
「参加の権利」を 4 軸に添えている。これらの権利のうちの「参加の権利」については、同
条約第 12 条の以下の2項を基本としている。
1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべ
ての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合におい
て、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとす
る。
2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続
において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当
な団体を通じて聴取される機会を与えられる。
さらに同条約の参加の権利をめぐる条約は以下に挙げられる。
● 児童は、表現の自由についての権利を有する。(13条)
● 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。(14条)
● 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。(1
5条)
● 締約国は、大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め、児童が国の
内外の多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の
福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができるこ
とを確保する(17条)
● 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び
及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する
権利を認める。(31条1項)
このように「参加の権利」は、意見表明、思想や宗教、結社、情報の入手、余暇活動、
文化的・芸術的活動、などと非常に多様であるが、いずれも12条に記されているように、
12
子ども当事者に関わる全ての事柄についての意思決定に機会に参加できるということを基盤
としている。
EU 若者政策
国連条約における子どもの参加の定義は EU 諸国を始め、程度の差異はあるにせよ影響力
を保持し、90年代には具体化へと進んだ。2009 年 11 月、EU 理事会は「青少年分野におけ
る EU の協力についての新たな枠組み(2010・2018)」8を採択した。これは、ポスト工業化に
おける欧州の若者を取り巻く社会経済状況、労働市場、少子高齢化による人口構造の変化を
背景に、若者自身の高学歴化、若年労働市場の流動化、消費市場の拡大と IT 化の進行によ
る若者の社会的関心の希薄化、という欧州共通の課題を指摘した EU 若者白書 2001 に次ぐ、
欧州の若者政策を前進させる画期的な決議であった。同枠組みでは、①教育・労働市場です
べての青少年に対する均等な機会の創出、②積極的な市民としての行動(active
citizenship)、社会的包摂(socialinclusion)、連帯(solidality)、を促進することに
合意した(CounciloftheEuropeanUnion,)。さらに、参加を含む、以下に掲げる8つ分
野を重要施策と位置づけた。
1) 教育と訓練
2) 雇用と起業
3) 健康と福祉
4) 参加
5) ボランティア活動
6) 社会的包摂
7) 青年と世界
8) 創造性と文化
このうちの第 4 つ目の参加について更なる詳細が付録にて以下のように記されていた。
参加
目的:全てのレベルにおける代表制民主主義・市民社会、社会一般において若者の
参加が支援されなければならない。
加盟国・議会のそれぞれの資力に応じた取り組み
8The Council of the European Union (2009)
13
● 国の若者政策に関する若者参加と若者と対話の仕組みの展開
● 民主主義社会における国・地域の若者会議とその重要性の認知の促進のみ
ならず、若者組織を政治的にも財政的にも支援すること
● 若者参加・情報・協議に関する既存の及び開発中のガイドラインの使用を
奨励し、活動の質を高めること
● 代表制民主主義、若者組織及びその他の市民団体における多様な若者の参
加を促すこと
● 若者の参加を広め、深めるためも情報、通信技術の効果的な活用
● 早い年齢から学校教育、ノンフォーマルな学習を通じて様々な形態の『参
加のための学び』を支援すること
● 公共機関と若者間でのディベートの機会のさらなる展開
以上からも明らかなように、同枠組みでは今日の代表制民主主義社会・市民社会を基盤に
多様な方法(若者組織、対話、教育、公共機関とのディベート)を通じて多様な若者が参加
できるための、あらゆる夏期を提供することをその主目的に添えている。Loncleetal.
(2008)による、ヨーロッパにおける若者の社会参加の類型では、政治的参加、社会的参
加・市民参加、利用者(ユーザー)参加、教育・雇用を通じての参加という四類型を上げて
いるが、上述したの欧州若者政策の対象者であり、利用者である若者本人の参加の重要性が
強調されていることがよくわかる。これに従って、若者の参加のために不可欠でもあり参加
の初期の段階で必要とされる情報の提供については『欧州議会が、欧州若者ポータル
(EuropeanYouthPortal)を更新し、若者へのさらなるアウトリーチ促す』として具体的な
施策へと繋げている。
スウェーデンの若者政策
今日のスウェーデンの若者政策が形作られたのはここ 30 年くらいであるが、19 世紀後
半、20 世紀初期における学校教育、余暇活動の組織が形成されたことが若者政策の起源と
言われ、長い間この2本柱がスウェーデンの若者政策を支えてきた。1960 年代には余暇活
動やクラブ活動が若者政策の主要な部分を担うこととなったが、1970 年代にはこれまでの
部門別の若者政策からより包括的な若者政策への転換が成された。そして 1985 年に国連が
国際青年年を宣言したことを発端に、さらなる改革が始まった。まず 1986 年に若者大臣
(YouthMinister)が初めて任命され、1994 年に若者政策(Ungdomspolitik)、1997 年に若
者のための政策(Politikförunga)、そして 1999 年に若者政策法(Genomden
ungdomspolitiskapropositionen)という3つの若者政策が施行された。青年事業庁
(Ungdomsstyrelsen)は 1994 年に設置された。
14
2004 年秋、国会で新たな若者政策、『決める力-福祉の権利』(Maktattbestämma–
rätttillvälfärd)が可決され、新たに2つの若者政策主目標が定められた。
・若者の影響力への実質的なアクセスを保障すること。
・若者の福祉への実質的なアクセスを保障すること。
この目標は若者一人一人の生活や地域の環境を向上させるだけでなく、社会全体の発展も
意図している。さらに、家庭、学校、仕事、友人との関係性にも重きを置いている。若者が
影響力を持てるようにすることの理由に、ひとつはまずは「それ自体が権利である」こと、
そしてもうひとつは、「若者の知識と経験は社会の価値ある資源である」という認識の共有
が挙げられる。『若者は社会の資源である』”Youngpeopleasresource”は、様々なスウ
ェーデンの政策文章で繰り返し出てくる言葉のひとつである。2009 年の 11月に EUが 2018
年までの新しい若者政策のドキュメント「EUの若者政策の新たな枠組み2010‐2018(A
renewedframeworkforEUcooperationintheyouthfield2010‐2018)を採択した時に
スウェーデンは議長国であったため、その際に「若者は問題解決の対象なのではなく社会の
リソースなのだ」というスウェーデンの認識が EU 内で共有することができたという。
さらに政府と国は、意思決定者(政治家など)が若者向けの公の活動をするときに、常に
考慮しなければいけない点として、①社会の発展のための資源であり、②権利を有している
こと、そして③自立した個人であり④多様である、という 4 点である。
以上を踏まえて、スウェーデンの若者政策には以下の 4 つの特徴があげられる。
• 若者政策(ユースポリシー)の対象を 13 歳から 25 歳としていること。
• 広範囲にわたる政策をカバーしていること
• 全ての若者へ、自立した大人になるための機会を提供するユニーバーサルな政
策であること。
• 若者を社会のリソースとして見ていること。
これは EU 共通の課題として浮上している若者の社会的地位の低下を認識した上で成り立
っていると鑑みるみることが可能なので、労働的側面、教育的側面、政治的側面、文化的側
面など多様な分野における若者の影響力を高める必要性を説いているといえるが、以下では
とくに、余暇活動的側面におけるスウェーデンの若者参加を概観する。
余暇活動政策
広範囲を領域横断的に扱うスウェーデンの若者政策は大きく5つの部門(仕事、家族、余
暇活動、学校、政治)に別れており、以下では主に余暇活動政策、特に余暇活動施設政策・
ユースセンターについて記述する。
スウェーデンのユースセンターの一般呼称は”Måtplats”(英訳で MeetingPlace)であ
り、和訳するとそのまま「出会いの場」である。基本的には全ての若者に開かれており、特
定の若者だけを対象にせず様々なプログラムを提供している。これらの活動のことを開かれ
た若者活動(OpenyouthActivity)と呼び、職員である余暇活動リーダー(Fritidsledare)―
15
所謂ユースワーカーである―または施設の運営に携わる若者から構成される「若者運営委員
会」により提供、企画化されている。活動内容は非常に多岐にわたり、おしゃべり、相談、
カウンセリング、宿題の手伝い、音楽、TV ゲーム、ハイキング、イベント、映画、ボラン
ティア活動、職業訓練、工芸、アート、スポーツ(バスケット、バレーボール、サッカー、
水泳)などである。日本の児童会館の若者世代向けと言ってもいいだろう。
施設の種類は主に以下の区分によって定義が異なる。
・若者クラブ(Youthclub),余暇施設(RecreationCentre)–13 歳から 16 歳の若者対象。
(90 年代、減少傾向)
・ユースセンター(YouthCentre),活動施設(Activitycenter),文化施設(Cultural
Centre)–15 歳から 20 歳までの若者対象。(90 年代に増加)
中にはこれらの区分けに当てはまらない複合施設も存在する。
余暇活動支援の歴史
1970 年代、これらのユースセンターや余暇施設では若者の飲酒などによる問題でユース
センターでの若者の活動の質の低下が目立った。当時、ユースセンターに若者をとどめてお
くことは、「社会的な問題を防止する役割を持つ」とみなされていたが、同時期に提案され
た新たな案の提案は斬新的なものであった。
「若者世代には、財政などにも影響を与えることができる実質的な意思決定力が与
えられるべきであり、出会いの場(MeetingPlace)は、職員と若者が施設の運営や
計画にともに責任を持ち自治を機能させなければならない。」(Ungdomsstyrelsen,
2009)
これがスウェーデンの余暇活動における若者政策を支える大きな価値、方向性の転換であ
り、健全育成、非行防止的な若者政策からより若者の参加を重視した政策へと志向するきか
っけとなった。1980 年代、これらの改善策に加えさらに、より若者に協力的な環境を整え
ることで、施設における民主主義を高め、若者の声が聞かれ、自尊心を高めるという結果を
もたらした。また施設に来る若者の地域社会への参加を促すことも目標となった。90 年代
には、より若者に責任をもたせることで影響力を強めることが新たな目標となる。このよう
な流れに従い、今日では「出会いの場」としてのユースセンターは若者の影響力を強め、社
会への参加を促す場へと変貌を遂げた。
課題と現状
しかし、それでも大多数の若者がこのセンターを利用していないという現実が一方では存
在する。スウェーデンの 16 歳から 25 歳の若者の 78%が一度もセンターを利用したことが
なく、一方で 11%の若者は、定期的に 低でも月に一度センターを利用している。また同
調査では、十分な教育を受けておらず、雇われていなかったり、病気の親を持つ若者はセン
ターを利用する率が高くなっているという結果も出ている。
16
さらにクラブ活動に代表される組合や団体の結成などの数も徐々に減ってきている。これ
は個人主義やインターネットの発達に伴う、ソーシャルネットワークサービスの普及をひと
つの原因にあげている。そして、ユースセンターにおける若者の活動でも、活動の計画、新
企画立案の段階からの参加ができていないため、動機付けをされないという問題もあること
が指摘されている。さらに近年では若者の活動も、新たに何か新しい企画を始めるよりも、
既存の企画やプログラムに一人一人の影響を与えられようにする機会を提供する、という性
質の変化もあり、これは参加を重視した政策の結果が現場レベルに染み渡った結果ともいえ
るだろう。
このような若者の段階的な参加を促すことにおいて、若者とユースワーカーとの関係性の
重要性が増してきているという報告も上げられている。ヨンショーピンという県の自治体の
センターに来ている若者のうち 10〜20%は、ワーカーが自分たちの声を聞いてくれていな
いと感じていることも指摘されている。
スウェーデンの若者政策における若者参加
参加の点に関して、スウェーデンの若者政策(特に余暇活動政策)で特に強調されるべ
き点、ひとつ目はスウェーデンの若者政策の目標である「若者の影響力への実質的なアクセ
スを保障すること」であろう。これは、若者の参加を促し社会へ実質的に若者の影響力が及
ぶことを保障することをその中核に添えていると解釈できるが、とくにあえて参加という言
葉を使わずに「影響力」という言葉を選んだところにスウェーデンの若者参加への力の入れ
具合を見いだすことができる。
そして第二に、ユースセンターを若者の社会的影響力を高める場として位置づけている
ことだろう。非行予防機能としての余暇活動施設から、自治を高め、影響力を高める場への
転換し、課題を残しながらも着実にその役割の変容を担ってきた。
影響力と参加
前項では児童の権利条約と EU とスウェーデンの若者政策について政策文章を引用するこ
とで、参加の方向性について整理した。その中で繰り返されるキーワードのひとつの「影響
力」が挙げられる。代表的なのがスウェーデンの若者政策の目標「若者の影響力への実質的
なアクセスを保障すること」であるが、それでは若者は影響力への実質的なアクセスがある
状態とはどのような状態なのであろうか。そしてなぜ、参加という言葉を使わずに、「影響
力」なのだろうか。
ここでは子どもの参加と影響力の関係性について「権力」に焦点を当てながら紐解いてい
く。ミカエル(2008)のフーコーの分析によると、権力とは、商品ではなくむしろ、ある実体
(人間や組織)が他の実体の作用に影響をもたらすための実体に対する行為が生じている状
況であるとしている。そして権力を、
17
● 「もの」ではなく、ある種の活動性を伴う一般的な言葉
● 特定の階層の人や組織の手のうちに集まっているというよりも、多様に散在してい
るもの
● 社会全体に配置され、小規模の現場実践を通じて行使されるもの
として明確化している。これらの論述から、子どもの権利は、ただ単に保持しているま
たは大人によって与えられているものではなく、現場レベルの多様な実践を通じてその権利
を子ども・若者自身が実際に行使しているときにより保証されるものと分析できる。加え
て、ミカエルは「参加の取り組みの効果」を対象に子どもの参加の調査をすることの必要性
について指摘している。これは参加のプロセスにおいて実際にどのような参加がなされてい
るのか検証することよりも、参加の結果どのような、影響・効果・成果が子ども参加の結果
に現れたのかを重視することの強調である。さらにフーコーは、権力の調査は
「『では、いったい誰が権力を持ち何を企んでいるのか?権力を所持している人の目
論みは何か?』という迷路のように入り組んだ答えようのない質問を投げかけな
い。その代わり、実際的で効果的な実践に向けられたその権力の意図—もしあれば—
がどこにあるのかという点から調査することはあり得る。必要とされていること
は、その権力が向けられている方向性やその目標や対象、適用範囲などの仮にでも
私たちが想定できるものとの直接的な関連性といった点からの権力の外からの様相
に対する調査なのである」(Foucault,1980b:)
と、権力の行使の結果をその目標や対象、適用範囲などの具体的な指標に照らし出すこ
とを述べている。権力の目的が表出する先は、その 終的な結果であって、権力を行使する
当本人の意図のなかにあるわけではないということである。その他にも、Kirby(2002)や
Lansdown(2004,2006)もまた、子どもの参加は成果と影響力によって分析されるべきだとい
う主張してる。こうした主張に支えられて欧州の、特にスウェーデンの若者政策は「若者の
影響力への実質的なアクセスを高めること」を具体的な目標に添えて子ども・若者参加を推
進してきたと言えるだろう。
こうした整理を踏まえ、次項では如何にして若者の参加が実際に促され、もしくは若者が
参加をし、彼・彼女らの影響がその成果として現れているのかどうか、についてスウェーデ
ンのあるユースセンターをケーススタディとして扱い、これらの疑問に答えていくとする。
18
第三章 ケーススタディ:ストックホルムのユースセンターの事例
調査方法
筆者は、ケーススタディを質的調査方法・インタビューを用いて研究命題に応えていくこ
ととした。ブライマン(Bryman,2008)によると、ケーススタディの基本となる方法と原則
は以下に挙げられる。
● フィールドワークは、単一宇の場所で実施されるべきであり、それが意味するの
は今調査が例証となるということである。
● ある種の対象を代表するために用いられる典型的な事例を特定することは不可能
である。
● ケーススタディは、必要以上に誘導的なアプローチと結びついてはならない。理
論構築、理論検証と関連づけうるものである。
さらにブライアンは、質的調査におけるインタビューの基本原則について以下のように指
摘した。
● 質的調査は、初期の調査構想の形成における一般性とインタビュイー自身の視点に
重きを置いている。
● 時には本筋から外れることも奨励される。それは、インタビュイー自身が何を重要
と考え、関連があると考えているかを考察する見識を与えてくれる。
● 質的インタビューは、インタビュイーがインタビューを受け、実施する中で生じた
深刻な問題の結果に応じて主眼点を調整して、柔軟に対応して進行される。
● インタビュイーは時には、数回にかけてインタビューを受けることになる。
これらの原則と方法に従い、2012 年春、本研究に関するインタビューを実施した。イン
タビュー相手は、スウェーデンの首都ストックホルムの南に位置するハールホルメン地区
に位置するユースセンターに所属する職員2名と、同施設の利用者であり運営を担ってい
る若者2名である。
2012年 4月半ばにアンドラ・ヘメットという名前の余暇活動施設を訪問し、 初のインタ
ビューを実施した。インタビュイーは、同施設職員であり当施設を含むハールホルメン区5
つの施設の総責任者でもありユースワーカーである、スザーナ・ブロリンで、構造化され
ていない質問で 90 分間インタビューを実施した。音声録音と実名公表はインタビューの同
19
意を得てから行なった。
その一ヶ月後である 2012 年 5 月、同施設の館長であるカロリン・ツーリンと施設の理事
会と関わる2人の若者とインタビューを行なった。ガブリエラ・ヨゼフは現在 18 歳で、か
つて施設の理事会に所属しており現在はパートタイムでこの施設で働いている。ムハンマ
ド・イッサもまた 18 歳でこの施設のジュニアリーダーであり、いくつかのグループや理事
会で代表も努めている。同じように、音声録音と実名公表の同意を得て調査を実施した。次
項では、インタビュー、提供していただいた資料とウェブページ、文献から得られた情報で
施設の概要とその成り立ち、現在の活動、そして課題について記述する。
20
施設の概要
アンドラヘメット・ハールホルメンの若者の家(AndraHemmet:Ungdomshusi
Skärlholmen)というのは、AnotherHouse:YounghouseinSkärlholmen という英訳にな
り、若者にとっての「第二の家」という意味である。この地域の若者の余暇活動をするため
の文字通り「出会いの場」(MeetingPlace)となっている。9ストックホルム南の
Skärlholmen(ハールホルメン)という自治体に位置しているこの地区(Vårberg,Sätra,
Bredäng を含む)に位置する 大のユースセンター。33000 人の住人のうち 48%がスウェーデ
ン国外の出身で、70 の異なる言語が混じり合うほどの移民が多い地域であり、うち 19 歳以
下の若者は 26%である。10
ハールホルメン自治体は、社会福祉課、子ども若者・余暇活動課、高齢者・障碍者課、地
域サービス課、行政課の5つの部門に別れており、このユースセンターは子ども若者・余暇
活動課に属し、自治体から全面的に資金が出ている。
施設
当施設は以下の各設備から構成される。
外観
9 当施設ホームページ参照 http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=86aeb03b3c774caf947fa2af9a56b794 10 インタビューの際の配布資料より
24
対象と開館時間
基本的にここは 12~19 歳の若者を対象にした施設である。スウェーデンの若者政策による
と 13~16 歳対象は”ユースクラブ”・”レクレーションセンター”という呼称で、15~20 歳
対象は、”ユースセンター”・”アクティビティセンター”・”カルチャーセンター”とい
う呼称になっている11のでこの施設は複合型の施設ということになる。そのため、他のセン
ターよりも多様な層が来るため開館時間も年齢や性別によって多様に設定している。基本的
には 17 時から 22 時までだが、12~15 歳の若者は月曜日と土曜日は 17 時から 20 時まで、水
曜日は 12~19 歳の女の子の日で、18 時から 21 時までとしている。12
施設の成り立ち
若者とユースワーカーによる協同でのセンターの設立
このセンターは5年前までは廃止された警察が利用していた施設だった。遡ることさらに
その2年前、スザーナがハールホルメン区に来て働き始めた時、ほとんどの自治体の仕事の
対象が大人に向けられたものでありそのことに疑問を感じ、この地区の責任者にその疑問を
ぶつけたところ、許可がおり若者向けのプロジェクトを始めることになった。実際にその
後、この地域の住人を集めて対話集会を開いて、 も関心のある問題は何かを聞いたとこ
ろ、ほとんどの人が若者のことを大変恐れていることが明らかになった。そこで若者を巻き
11 Ungdomsstyrelsen, 2010, FOKUS 10 12 当施設ホームページ参照 http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=86aeb03b3c774caf947fa2af9a56b794
25
込んで若者のためのセンターを作ることになった。
スザーナはまず始めに立ち上げを手伝ってくれる他のユースワーカーを集め、その後、
若者がいる場所に出向いて一緒に働いてくれる若者を募った。このときの目標人数は 15 人
だったが、予想に反して 終的には 100 人を超す若者が集まった。人数が多かったので小さ
い異なるグループにわけてプロジェクトを進めることにした。その中の 10 人の若者とこの
荒れた施設を下見にいくことになった。若者達は 初は自分たちがセンターをたてるという
ことに半信半疑で、「ちょっと見にくるだけでいいから、いつでも帰っていいから」とお願
いして、なんとか下見にきてもらったという。腐敗したセンターを実際に目の当たりにする
やいなや、「もし自分がこの建物を変えれるなら、あなたの右腕になるよ!」と言った。さ
らに腐敗した施設の奥まで入り、全て見終わって出てくるやいなや「もし自分がこの建物を
変えれるなら、あなたの左腕にもなってみせる!」と言った。こうしてプロジェクトは始ま
った。
若者と働く大人にとって若者は何ができるのかを見極めることが大事であるとスザーナは
言う。また、「若者自身が参加を望んでおり、若者自身ができると信じて、他の人たちを感
じれるようにすること、が立ち上げでは特に重要です」と付け加えた。 終的には 1 年半で
この施設以外にも3つのセンターを設立。センター設置後も参加の仕掛けは続く。
センターに来る若者を想定してグループを作り、どのように若者に働きかけるかというこ
とを若者達に議論してもらった。例えば、イベントホールを使うであろうスポーツをしにく
る若者達にとって、どのような施設の内装にしたらいいかというのを話し合うのではなく、
この若者達に「どのように自分たちは働きかけることができるか」というのを話し合っても
らった。
運営委員会、グループ
以上の流れを受けてできたのが、各センターごとの運営委員会やグループである。もちろ
ん全てセンターを利用する若者から構成される・
● イベントグループ:サッカートーナメント、パーティーなどのイベントの実行をる
グループ
● ピラ・ダンサーズ:12~19 歳の若者にダンスのトレーニング、レッスンの機会を提
供する
● 127PlayEntertainment:余暇活動、音楽イベントなどの企画のスタートアップを
手伝うグループ
● 日曜日チーム:障害を持った若者への働きかけをする
● ショーチーム:イベントを企画する際に、他のユースセンターや大学、フォルクと
いう市民学校とのコラボレーションをマネージするチーム
● 若い親:子育てを協同でやったり、ベビーシッターを提供するチーム
● センター運営理事会:センターの運営をするグループ。一ヶ月に一回の定期的な会
議で予算や、イベント、設備などセンターの若者に関する全てのことの意思決定を
行う
職員・スタッフによる参加の促進
26
同施設には現在(2012 年)12 人のユースワーカーが務める。DEMOKRATISLAGET という本を
スザーナとこのセンターのワーカーで出版し、若者参加を行う上でのエッセンスなどを共有
している。この本では新たな方法論を提示しており、どのようにしてワーカーは若者から学
ぶことが出来るのかというのを記述している。
運営委員会のメンバーはセンターに来る若者達によって選挙によって選ばれ、今期は5人
が運委員会のメンバーである。この会議で、ボードゲームや、テレビゲーム、イベント、
諸々のスケジュールそして、それぞれの上述したグループへの予算配分をする。会議でもし
アイディアが出たら、全て書き出してその場でそれをやりたいかどうか、やりたい人がいる
かどうかを若者に聞く。もし誰も賛成しなかったら、アイディアを保留しておき、運営会議
以外の場で若者達に聞き続け、可能性を探る。
またアイディアについて議論の余地があってすぐに決めることができなかったとき、後
日、確実にフィードバックをすることが大事である。予算の関係でできなくなったとしても
そういったアナウンスを確実に伝えることが重要である。もし若者がせっかく出したアイデ
ィアがフィードバックをもらえずほって置かれたら、声を聞いてもらえていないと感じる
し、聞くふりをしているだけだと感じてしまうことになってしまうからというのがその理由
である。ときには代替案を示すこともある。
また会議でアイディアをすくいあげるだけでなく、日誌で若者のアイディアを拾い上げる
試みもある。ワーカー同士での仕事に関することを共有する日誌だけでなく、若者からでて
きたアイディアをその進捗状況を記述する枠が日誌の中にある。
27
左からどんなアイディアが出たのか、誰が提案したのか、締め切り期限、と別れており、
緑色の枠は現在進行形のアイディア、黄色はこれから始まるアイディア、赤は議論の余地が
あったりキャンセルされたアイディアを示す。(この図はワーカーからいただいた資料の本
の一部。プライバシー保護のため名前は削除している)肯定的なコメントを載せ
る”Positivefeedback”欄もある。もともとはこのように構造化された形式ではなかった
が、今年からこのように構造化されることになった。
28
運営委員会のコンペ大会
ハールホルメンにある5つのユースセンター間での行われる、運営委員会同士のコンペ大
会も若者の参加を促す取り組みである。競争はポイント制で行われる。会期が終了するとき
に(運営委員会メンバーの任期である1年間ごと)、 もポイントを稼いでいた運営委員会
が勝ちとなる。順位に応じて報償があり、昨年優勝した運営委員会はブリュッセルにいき
EU 議会に参加した。2位以下はスウェーデン内の地方のセンターとの交流プログラムへ移
る。ポイントは様々な方法で稼ぐことが出来る。イベントでの来場者数や、効率的なミーテ
ィングのやり方、メモのとりかたなどをワーカーが評価して、ポイントを与える。他にもミ
ッションを解決して稼ぐことも出来る。このミッションはワーカーから課される。例えば、
人種差別問題についての新聞記事を書いてもらい、プレスリリースし、採用された記事の運
営委員会はポイントを獲得する。
このコンペの目的は、より多くの若者を巻き込むことと、運営委員会の質の向上である。
しかし 近、このコンペ大会は廃止された。理由は、運営委員会の若者達の活動の動機がポ
イント稼ぎになってきかねないこと、センター設立当初よりも運営委員会が定着してきてポ
イント制によるインテンシブを与える必要がなくなってきたこと、運営委員会のメンバーだ
けしかこのコンペに参加できないこと、などがあげられる。このコンペに関してのインタビ
ュイーの意見には次のようなものがある。:
ガブリエラ:
“Now there are other things to do so if they know that they are going to win, something
may be they wonʼt like a „I donʼt want to go meeting I stayed home and PlayStation‟
instead. It gives them to a way to do it and it helps them, it helps AndraHemmet, it
makes everyone happy when they want to because I learned lot of being in the board. ”
イサ:
“I donʼt think competition is something. Iʼm not in the board because it is something like
it is an experience and I learned a lot and something fan because I get to be a part of the
…… this place and Iʼm now in the board because I want to help this place better and
better. So I donʼt think it is not about competitions. And it makes me feel like Iʼm
important in this place and I get to decide to certain things like teenagers so it is fan. ”
ガブリエラは、そのコンペ大会がなくなったときの若者の動機付けがなくなった時に、運
営委員会の活動の停滞を心配するのに対して、イサは運営委員会はコンペ大会が全てではな
29
く、 終的にこの場所(ユースセンターや地域)をよくしたいから参加しているのだとい
う。代替案として現在実施されているコンペは、センター単位でのコンペである。評価基準
はあまり変わらないが、今度はセンターに来る全ての若者が参加できるようになった。
スタッフ制度
2013 年春から、運営委員会メンバー経験者のみが申請することができる有償のスタッフ
制度を採用することになった。といってもフルタイムではなくパートタイムである。毎月第
2土曜日だけ運営委員会の会議に来て、会議のサポートをしたり、他のグループの面倒をみ
たりする。ガブリエラがやっているのもこのパートタイムのバイトである。
もうひとつがジュニアリーダーとして働く制度である。1学期間だけ何かのチームのリー
ダーになって責任ある立場を経験してもらう。 年少は 21 歳が2人いて、どちらも昔この
センターに通っていた。目的は、若者と責任を分担することと、ユースワークというのはど
ういうものかというのを体感してもらうことである。結果的に正規社員として働きたくなっ
た時には、大学にいって学位をとらなければいけないが、そういうきっかけを提供してい
る。経験者がこのような立場になることで、 も効果的な活動を進めることが出来る。ワー
カーよりも彼らのほうがより若者に距離が近いからである。
課題
それでもスタッフ自身はまだまだ若者の声を聞けていないと課題を指摘している。若者自
身が望めば、なんでもできるが若者自身がそれを望んでいない。多くのセンターに来る若者
達の興味は、Xbox やプレイステーションなどになっていてそればかりをしている。なぜな
らセンターに来る若者はセンターの”中”で生活をしているから発想が室内の活動に傾倒し
がちであるからである。しかしスザーナ自身は、彼らがやりたいことだからそれでいい、そ
れが私たちの仕事だと言い切る。センターに来ない若者がなぜ来られないのかという理由
は、TV ゲームや iPhone などに代表されるように余暇活動がより”個人化”していることを
指摘彼女は指摘している。また Facebook などの SNS などによるコミュニケーションの変化
もあると触れている。
30
実際の若者の参加度合いとその方法
ここの若者は実際にはどのくらい参加できているのか?
大事なのは、課題をとりあげて予算内で何を買い何をするかを決めるのは運営委
員会であり、センターに来ている若者がやりたいことから始めること。もし誰かが
ここにきて、これこれこういうのをやりたいんだけどと、私のとこに来たら「私は
決められません。若者達にあなたがこの話しをしたがっていることを聞いて、許可
をもらわないといけません。」と言います。若者民主主義のためには意思決定こそが
全てなのです。(スザーナ)
スザーナは、センター内での仕事だけでなく、常に政治家とコンタクトをとりロビー活動
をしている。さらに、 近始まった UNG127 というプロジェクトでは 18 歳のイサが代表を
務め、ハールホルメンを若者にとって住みやすい場所にするための対話の機会の場を作り出
している。この活動は 2011 年の春から始まった。興味深いのは、この UNG127 がもともとは
クラブ活動などのスタートアップ支援から始まっていることである。またイサはこの機会で
政治家にアドバイスをしているとも発言をしていた。
以下には、テーマを「若者参加」に絞ったスザーナとのやり取りのみを記述する。太線は
筆者は聞いた質問である。
(筆者)若者参加のうえで重要なことは何ですか?
(スザーナ)この施設を建て、参加することになった若者が、この施設が自分の
ための一部分であり、何かを変えることができる自分の場所であると感じることが
大事です。また、社会にとって一人一人が大事で、社会の一部であることを信じれ
るようになることがとても大事です。また、ユースワーカーは『大人の友達』であ
るべき。例えばもしある若者がきて「今から言うことはすごい大事なことなんだけ
ど、誰にも言わないでね。」と若者に言われたとき、「わかった誰にも言わない」と
いうのは簡単だけど、ユースワーカーはこのときだけは大人でなきゃいけない。も
しその若者がドラッグを使っていたり、手首を切っていることがわかったら、その
解決のために行動しないといけない。なぜならユースワーカーであり、ソーシャル
ワーカーであり、ソーシャルワーカーの倫理に基づいかなければいけないから。そ
のためにはある程度の専門的な知識を兼ね備えていなければいけない。コミュニケ
ーション能力の高いだけの医者と、学位のない医者、コミュニケーション能力も高
く学位もある医者だったらどの医者がいいか。だから専門性も大事です。
(筆者)若者参画を促す時に、よく陥りがちな例として若者が本来が決めること
を大人が事前に全て決めてしまうという、偽の参画もありますが、ここではどうな
んでしょうか?
(スザーナ)そのようなことに陥らないために2つの重要なことがあると思いま
す。ひとつは、センターの建設の前の 初にミーティングがあったとき私は1人な
31
のに対し、若者達は 100 人だったということ。圧倒的な人数の違いで彼らがマジョ
リティーだったので、彼らがいつも勝つのです。そして、男性と女性の両方に参加
してもらうという、性に関しての配慮も非常に大事です。若者自身が意思決定する
こととジェンダーバランスの重要性を 初に決めて方針にしました。なのでいつ
も、この地区長(市長に近い人)と話す時には、これは私たち(ワーカー)がすべき
ことで、これは若者達が決めたことですと報告するためにも若者達の声を聞かなけ
ればいけないのです。たぶんこの長と政治家がユースワークに興味を持ってくれた
からこういうことができてるんだと思います。右派も左派も関係なしに関心を寄せ
てくれます。なので私の仕事のほとんどは若者によって決められるので、私は誰に
働きかければこの若者の決定が実を結ぶのかということに尽力しています。政治
家、学校長などがほとんどです。そのためには、自分自身が、ソーシャルワークの
団体に所属していることが大事です。 初の頃は、ここに来ている人たちがやりた
いことをやるというだけでしたが、 近、新たな方法での試みが始まりました。
Demokratislaget(Democracyteam)という名前の本を編纂し、ユースワーカーは
どのようにしたら若者から学ぶことが出来るのか、運営会議のための知っておくと
いい方法や知識などが載っています。他にもどのようにしたら若者にとって魅力的
な面白いことが出来るかなどなどです。これは、若者民主主義を作り上げるプロジ
ェクトと言ってもいいかもしれません。とても実践的なのでワーカーだけでなく、
若者が読んで活用できるようにもなっています。民主主義とはなにかとかそういう
ことも書かれています。しかしあいにく全部スウェーデン語です。私たちは民主主
義をもっと肯定的な方法でやっている。日々私たちがやっていること、それが民主
主義だと思います。そして主体的(proactive)でないといけません。自分が出来る
こと、自分が作り出せることの一部に属して主体的に貢献しなければいけません。
それが日常で も大事なことです。だからいつも若者と関わる時には、やりたいこ
とや問題提議、何を買うのかを意思決定するのは運営委員会であることがとても重
要です。もし誰かがここにきて若者と何かについて話したがっていたら、「私は決め
られません、若者達に聞いて希望を問わなければいけません」と言います。だから
本当に意思決定こそが全てであり、それが若者民主主義に欠かせないのです。それ
が民主主義です。
(筆者)しかし日本でも起きているように、代表制の民主主義は若者を社会から
排除することにつながらないでしょうか?どう思いますか?
(スザーナ)それはスウェーデンでも同じで代表制について議論してきました。
それ自体がどうかということじゃなくて方法のひとつなので、少なくとも重要な要
32
素の一部でしょう。しかし将来的には、今よりもっと哲学的に重要になればなるほ
ど、代表制民主主義だけじゃなくて、参加型の民主主義の重要性が増してくるでし
ょう。 初の話しみたいに、15 人の若者を集めようとしたら結局 100 人集まっちゃ
ったけどそのほうがなおさらいい。
(筆者)若者の非行問題も多いんですか?
(スザーナ)家族や、経済的に問題を抱えている若者がこの地区には多くいま
す。危機に瀕していると言えるでしょうが、私たちは決して問題とは言いません。
そういう地域に住んでるだけです。確かに多くの問題はありますが、ここはストッ
クホルム北部の地域ほど犯罪率は高くないのは、若者達を社会から排除させない取
り組みをしているからでしょう。それとここのスタッフが常に若者に対して献身的
で、次の段階へいくための方法を試行錯誤しているからでしょう。そのようにして
デモクラシーワークで有名になりました。また、障害を持った子ども若者への働き
かけもあります。スウェーデンでは、障害を持った子ども若者達は学校で障害を持
っていない友達を作るのに苦労しています。しかし私たちは新しい方法を発見して
ここで実践することができています。それも有名になった理由の一つでしょう。
(筆者)障害を持った若者ももちろん運営委員会に参加できるんですよね?
(スザーナ)もちろんです。今はいませんがかつていました。彼は障害があった
ため書くことができなかったのですが、どうしても書記をやりたいというので、選
挙で運営委員会に選ばれたら書記になれるとアドバイスしたら、一生懸命働いて、
終的に彼は選ばれて1年間書記を務めました。彼は本当に誇らしげでしたね。え
え。しかし、彼らは民主的な方法を用いて障害を持った若者へ働きかけたのです。
(筆者)この施設が出来たあとで、 高の若者参画の事例、ストーリーはなんで
すか?
(スザーナ)スウェーデンの国王がここに来て、視察することになった時の話し
ですね。普通のひとは、国王と会うことになったら「これから王様に会いにいくん
だ!」と言いますが、ここの若者達は自分たちのしていることに誇りを持ち、一生
懸命活動をしているので、私が国王が会いにきたがっているということを伝えた
ら、「国王がここにきて、私たちと会うことになった」と言っていました。これを聞
いて私は、彼らは、自分たちの仕事に誇りを持っているし、王様から何かを学ぼう
としており、国王と対等の立場の姿勢でいるように思いました。もうひとつは運営
委員会を経験したメンバーは全員大学や高校にいくことになったことです。 初に
33
会った時は、学校になんかほとんど行かなかったにも関わらずです。
(筆者)失敗したことはありますか?
(スザーナ)はいあります。運営委員会に成りたがっていた1人の若者がいたの
ですが、彼は多くの問題を抱えていたので何かをしたかったのですが結局出来ませ
んでした。学校にいかず、薬物に手を出し、暴力事件もありましたが、とても素晴
らしい子だったのでずっとコンタクトをとっていました。しかし、あるとき彼の親
が、ガンビアに帰ることを決めてしまいました。このとき彼は社会ににたいしても
のすごく怒りを覚えていましたが、私たちは何も助けることが出来ませんでした。
きっとギャングが絡んでいたはずです。
(筆者)ギャングも多いんですね。
(スザーナ)そうですね。私はギャングを恐れていないし、彼らがしていること
を絶対に許しません。一人一人の若者は受け入れますが、ギャングメンバーである
限りここに来ることはできません。ここにきたらここのルールに従わないといけな
いので、酒、たばこ、薬物は許されません。ギャングメンバーの勧誘目的にくるこ
ともできません。もちろん彼らがギャングを辞めたいと言ったら、私たちはできる
ことをなんでもしますがそしたら彼らはもうギャングの戻ることが許されないので
決めなければいけません。両方に属することは無理です。私はここにきた彼らと話
すこともできますし、もし彼らがここに来て助けが必要としていたら、もちろん助
けます。なぜなら私はソーシャルワーカーだからです。そうやってギャングと戦っ
ています。もしここに来ている若者でドラッグを使っていることがわかったらすぐ
にソーシャルワーカーに知らせることになっています。
(筆者)どうやってギャングメンバーを見つけ出すんですか?難しそうですが…
(スザーナ)正式なメンバーはギャングのジャケットを着ているのですぐわかり
ますが、正式なメンバーになるまえは見分けるのが難しいです。でもたいてい若者
と接していると、若者の口から聞くことが多いです。もし噂でもそういうことがわ
かったらすぐに本人に会い、本当にギャングメンバーになろうかどうかすぐに聞き
ます。そして、どういうことが起こりうるのかというをしっかり伝えます。
(筆者)危険なところですね。
(スザーナ)いやいやそういうわけでありません。わたしは決して恐れていませ
34
ん。多くの問題を抱えたギャングがいるのも確かですが、私たちがここにいるのは
彼らのために何かをしたいからなのです。
(筆者)昨年、イギリスへスタディツアーに行き、イギリスのユースワークをみ
てきました。そこでは、ヒアバイライトという若者の参画をグラフなどに書き込ん
で測定するワークブックなどをつかって若者の参画を促していました。そこで私が
学んだのは、彼らは参画というのを社会を変えて、影響力を発揮させることだと認
識しているということでした。何度も何度も繰り返して、参画とは変化を起こすこ
とだと強調していました。UK若者議会というのがあり、模擬選挙やシティズンシッ
プ教育も体系化されていて若者参画が政治と密接に結びついてるような印象を受け
ました。一方で、フィンランドでは、僕は行ったことはなくて友達が教えてくれた
のですが、フィンランドのある若者組織では、アントレプレナープロジェクト(企
画・プロジェクト支援)をやっていて、そこでは若者はどんなことをやってもいい
ということになっているというのです。なのでユースワーカーも 終的には何が起
きるかわからないと言っていたというのです。そこで僕の友達が言っていたのは、
フィンランドでは若者参画は、政治的なことだけでなく、ほとんどのグループワー
クや日常的なコミュニケーションなどの文化的な活動も含んでいるということでし
た。この考え方についてどう思います?若者の社会参画とはなんでしょうか?
(スザーナ)私たちはよりフィンランドのように考えていると言えそうです。ア
ントレプレナープロジェクトもありますし。だけど、イギリスみたいに政治家のた
めだけにやりたくはないですね。それを必要としている人のためだけにただ小さい
グループを作ってるだけですし。グループとは言えませんね。だから一番いいの
は、やりたいことをやってもらうのが一番なんです。フィンランドのやり方は参画
のための” 初のステップ”のためにとても重要です。始めのステップです。イギ
リスでやっていることは、 後のステップなんです。 初のステップなしにやって
いるのです。だからこうやって3つのステップを考えることが大事だと思っていま
す。一歩目は、フィンランドのやり方でプロジェクトをやって確実に目に見えるこ
とをやるのが大事です。それがフィンランドのやり方が意味していることでしょ
う。まずそこから始めるのです。そして次のステップにいくときは、何を学んだの
か、どうすれば社会を変えることが出来るのか、自分のできることで他の人に何が
できるのかということを考え、そして 後のステップにたどり着きます。なので私
は 終的には両方が必要だと思っています。だけどそれを繋げないと意味がありま
せん。そうすると大きな変化が起きるでしょう。この本(Demokratislaget)にもそ
ういうことが書いてあります。どうやってまず若者と関わり始めればいいのか、ど
35
うやって興味を持ってもらうのか、どうやって自分たちで組織化することに興味を
持ってもらうか、ということが書いてあります。またやりたいことを通すために
も、知識が必要なので、政治的な問題にも触れています。
(筆者)ユースワーカー以外の大人や市民は、若者の参画を促すためには何がで
きるんでしょうか?
(スザーナ)いろいろありますが も大事なことは、家庭などで若者の声にしっ
かり耳を傾けることだと思っています。若い時に社会や個人の問題について話し合
ったことがある子どもは、大人になったら問題を自分自身で解決しやすくなるとい
う調査を知ってますか?社会で起きていること、社会の問題について家庭で話す機
会がある子どもほど、大人になったときに自分で対処できるようになるというので
す。その逆に、子どもの前では世の中のことはうまくいっていて、幸せなことしか
考えていないように見せていると、子どもは社会に対しての問題意識を持つことが
なくなり、議論をしなくなり大人に成った時により多くの問題を抱えるようになり
ます。なので 初にできることは、常に若者と議論することです。議論することこ
そが、若者が民主主義の過程の一部になるために必要なことの全てなのです。他に
もここに来て、一緒に何かプロジェクトをやることもいいでしょう。ミーティング
をしにきたかったら大人でももちろん利用できます。もちろん大人としての振る舞
いを期待していますが。
(筆者)今日の日本の若者は議論ができなくて自分のことに関する事柄も決める
ことができないんですよ。スウェーデンでは多くのそういう機会があるように思い
ます。
(スザーナ)そうですね。先ほども言ったとおり、それはものすごく大事だと思
っています。学校でももちろんあります。しかしこれはどのような親のもとで育っ
たかの影響が大きいように思います。学術的なバックグラウンドをもつ親の元で育
った子どもは、やはり勉強しますね。しかしご存知のようにここハールホルメンは
様々な事情をもった若者達がいます。学校でうまくいかない子もいるので、同じよ
うなやり方ではできません。しかしそれでも議論することが大事なのは、ここにい
る若者達はものすごく様々な経験をしてきていて、他の国からきていて、議論しな
きゃいけないことを多く抱えているからです。どこかで何かしらの方法でやらなけ
ればいけないのです。
(筆者)たまに影響力を発揮しないで終わることもあるみたいですが。
36
(スザーナ)それは絶対にしてはいけません。若者にとって大事なのは、若者が
何かを起こすということなのです。もしなにも起こさなかったら、初めて私がここ
にきたときに会った若者と同じことになってしまいます。これまでずっと何も信じ
てこなかったのです。だからこそどんなに小さなことでも何かを起こすことを支え
なければいけません。約束しすぎな
ければ、何かしらの変化をみることができるでしょう。
37
終章 スウェーデンにおける若者参加の認識と課題
現場における若者参加
それでは、以上のインタビューを踏まえて現場レベルにおいて若者「参加」とはいかに解
釈され用いられているのかを検討する。まずは当該施設におけるユースワークについて重要
要素を抽出するのならば以下のようになるだろう。
1. 変えられるという実感を若者が持てる機会を提供する
2. あらゆる若者が関わることに意思決定をしてもらう
3. 主体性を伴うこと
4. 男女バランス、障害者や多様な層の若者を巻き込むこと
5. 代表制民主主義と参加型民主主義の価値観に基づいた若者の参加
6. グループの形成、ネットワーク化
7. 非行青年、社会的困難に瀕している若者に対するソーシャルワーク的アプローチ
この中でも 7 つ目の要素である「ソーシャルワーク的アプローチ」は一見、若者の参加を
促すユースワークの仕事のようには見えないが、これは子ども権利条約でも保障している権
利のうちの3P のひとつ、ProtectionRights(保護の権利)の保障であり、Participation
Rights(参加の権利)が強調されがちなセンターの中でも、子ども・若者の安全を守るた
めの 低ライン維持するために不可欠であるのだろう。
上述した7つの要素のうち 1 と 2 は、若者の参加・影響力に関わるものである。若者自
身に関わることを自分の手によって意思決定すること、そしてその結果、自分が意思決定し
たこと=参加に対して「変化」をもたらすことで、変えられるという実感を手にすること=
影響力を高めるという結びとなるのだろう。
また、余暇活動における「参加」に関してスウェーデン青年事業庁によると、以下のよう
な記述がある。
定義が強調しているのは、「参加」とは、若者にとって重要な決定と行動に影響力と
責任を持つことである。(Ungdomsstyrelsen,youthinfluence,2009)
この引用文は、EU 加盟国のユースワーカーが集まったヨーンショーピン地方自治体にお
いて開催された若者の影響力に関するセミナーの報告書からであるが、参加と影響力の関連
38
性を端的に現している。加えると、若者の影響力に対するアクセスの保障を唄うスウェーデ
ンの若者政策の目標と一致している。
加えて、スウェーデンには各地域・コミューン(自治体)ごとに「若者会」(Ungdomsråd)
なるものが存在する。2003 年に設置された組織であり、「コミューンの政策に若者の声を反
映させること」「若者をエンパワメントすること」を目的とした非営利団体であり各地域・
コミューンごとに設置されている。若者会の設置が自治体に必要とされた場合に、自治体に
若者会が設置されることになっている。地域・コミューンの若者の声を届け、若者の影響力
を発揮させるために、政策決定者へのロビイング活動や討議の場提供等を行なっている。
(NPO 法人 Rights,2010)このようにして、余暇活動施設外においても代表民主主義的な原
則に従い、若者にとって国政よりも身近な機会の場で実際に声を届ける機会を設けている。
3つ目の要素「主体性」に関しては、筆者は開かれた若者活動(OpenYouthActivity)
が鍵となると考える。「開かれた活動」の対語を考えるとしたら、所謂「参加型活動」がそ
れに該当するだろう。ここでいう「参加型」とは、既存の「準備された」活動に若者が参加
するという、より能動性と主体性を始めの時点では要さない活動のことである。「参加型」
活動のよさは、その手っ取り早さ、アクセス、参加の手軽さにあるが、弊害としては参加者
である若者を「客体化」つまり、お客さんとしてしまい受動性を生み出してしまう点であ
る。 悪のケースでは偽りの「お飾り」参加に陥ることもあるのだ。そういった意味で、オ
ープンな活動においては、やりたいことから初めてもらうという点で、「主体性」が重視さ
れるため、偽りの参加に陥る可能性が軽減されるのだ。彼・彼女らが実現したい、始めた
い、変えたい、起こしたい、創りたい、決めたい、責任をとりたい多種多様な活動から始め
ることができのがその特徴である。これを裏付けるようにしてミカエル(2008)は、権力を
● 「もの」ではなく、ある種の活動性を伴う一般的な言葉
● 特定の階層の人や組織の手のうちに集まっているというよりも、多様に散在してい
るもの
● 社会全体に配置され、小規模の現場実践を通じて行使されるもの
としているが、これを具現化しできる場として「開かれた若者活動」が機能しているこ
とは明瞭だ。
そしてこの始めの参加のステップから、次なる参加のステップへと進むことができるので
ある。子ども・若者がやりたいことから始めることができる開かれた活動に関して、スウ
ェーデン青年事業庁は、その可能性と必要性を以下のように記している。
39
民主主義の参加の視点から主張できるのは、身近な状況での小規模な活動への参
加をトレーニングすることは、連鎖反応的に異なる状況の活動へ参加することにつ
ながる傾向があるということである。このような意味においては、開かれた若者活
動は、それ自体に価値がある民主主義の訓練のためのプラットフォームを提供し、
願わくば、その他の状況での民主的な参加のための機会を増やすことになるだろ
う。(Ungdomsstyrelsen,2009)
これを裏付けるような事例が UNG127 というイサが所属していたプロジェクトである。
UNG127 は、ハールホルメン区を政治家と対話をすることでよくしていく活動をしている。
この活動はもともと施設内から始まったもので、他の若者の余暇活動の実現をサポートする
ことを当初の活動としていた。現在は活動の範囲は施設内に限ったものではない。さらにイ
サ自身は、高校生時代には「模擬選挙なんてただの冗談」と言っていたように政治には無関
心であった。この施設に訪問し始めた時は、ただサッカーやテレビゲームをしていただけで
あった。施設の常連になり運営委員会の選挙に興味をもち選出されてから運営委員会として
のキャリアを始めた。その後、政治が変わる必要性を実感し、UNG127 でも地域活動を開始
した。彼が歩んできた道筋が示すのは、若者が活動に参加することは、成長をもたらし、他
の状況でも民主的な参加をできるようにするために影響力を高める必要性を感じることをも
たらすということである。
このような文脈に乗っとり、アンドラヘメットにおける若者参加は、スウェーデン青年
事業庁による方向性に沿って、実現されているということができるだろう。
スウェーデンの若者の「実際の」社会への影響力とその課題
前述の内容からも、この施設の利用者であり運営者である若者の参加は非常に多様で、実
際にある程度の影響力を持っていることが確認できた。
しかし一方で、
• スウェーデンの 16 歳から 25 歳の若者の 78%が一度もセンターを利用したことが
ない
• 11%の若者のみ、定期的に 低でも月に一度センターを利用している
• 十分な教育を受けておらず、雇われていなかったり、病気の親を持つ若者はセン
ターを利用する率が高くなっている
• 個人主義やインターネットの発達に伴う、ソーシャルネットワークサービスの普
及が原因で、クラブ活動に代表される組合や団体の結成などの数も徐々に減って
40
きている
• ユースセンターにおける若者の活動でも、活動の計画、新企画立案の段階からの
参加ができていないため、動機付けをされていない
• 近年では若者の活動も、新たに何か新しい企画を始めるよりも、既存の企画やプ
ログラムに一人一人の影響を与えられようにする機会を提供する、という性質の
変化
• 16〜25 歳の若者で過去 12 ヶ月の間で団体/組織のミーティングに参加した若者の
割合は 29%13
といった、余暇活動施策おける課題もスウェーデン青年事業庁により報告されている。これ
らの報告が意味するのは、スウェーデンのユースセンターおけるユースワークは、若者の影
響力を 終目標に添えた「参加」を志向し、ターゲットアプローチではなく、「開かれた若
者活動に」に代表されるように包括的なアプローチを行なっているにも関わらず、所謂、社
会的困難層(教育・雇用・病気など)の子ども・若者が集まりがちな場所へと変容しつつあ
るということだ。これは、近年スウェーデンで指摘されている、海外の背景を持った人とそ
うでない人の格差が上昇しているという実体に伴った、地域間の「隔離」問題(特に移民が
集まる郊外とそれ以外)そして若年層の失業率の上昇が帰結といえるだろう。
(Ungdomsstyrelsen,2009)
さらに、調査中に注目に値する若者参加に関する統計を発見した。スウェーデンの若者
(18~26 歳)の 2006 年の選挙投票率は 71%であり、それ以上の世代の 82%に比べれば、低い傾
向にある。それでも日本の若者の投票率に比べれば遥かに高い水準を維持している。
青年事業庁,2010,FOKUS10
しかし注目すべきは、投票率ではない統計である。スウェーデン青年事業庁によると、
13 Ungdomsstyrelsen, 2010, Ung idag
41
• スウェーデンの 6%の若者(16~25 歳)が、政治的な決定に影響を与える実質的な機会が
あると感じており、
• 15%の若者が、自分の自治体の政策決定者に対して、自分の意思を伝える実質的な機会
が十分にある感じている。(Ungdomsstyrelsen,FOKUS10,2010)
どちらも政治的な若者の参加であるが、なぜ、同じ参加でも投票率と政治的意思決定への
参加というだけでこれだけの「ひらき」があるのだろうか。
欧州議会は、代表制民主主義社会における若者の参加を促進することを謳ったが、この2
つのデータの差は、現場レベルと国政レベルを橋渡しする「参加の梯子の欠如」とその困難
さ、代表制民主主義の限界を示唆するものである。代表制民主主義を否定する訳ではない
が、スウェーデンの若者は実際には何も変わらないという認識を以てしてしぶしぶ投票をし
ているのではないかという疑問を想起させたのだ。実は、これに関して、前述したインタビ
ュイーであるイサとガブリエラはこのように語っていた。
筆者:スウェーデンの選挙投票率がこんなに高いのは、模擬選挙を学校でやってる
からかな?
ガブリエラ:多分そうだと思う。政治についてより学べるからね。
イサ:だけど僕にとっては、ジョークみたいなもんだよ。10 代にとっては「おもし
ろいからよくないほうに入れてやろう」というもんだし。
カロリーン:まあ結局関係ないからね。
イサ:けど実際高校でやった時は、僕にとって十代じゃなかったから本当に差別主
義的な政党に投票したよ。
ガブリエラ:私は、多くの若者は私が投票しないことなど気にしていないからとい
って投票しているとは思いません。前回の選挙で私がもし投票しなければいけなか
ったら、多分どこにも投票しなかったでしょう。なぜなら、これは大きなことだ
し、よくわからないことだから、選ぶのが怖いんだと思います。
これらの言及が示しているのは、国政レベルの選挙に対する無関心と影響力を行使するこ
との難しさである。国政レベルの政治的決定に対して影響力を行使できないという気持ちか
ら、自分には関係がなくなっているように見えなくもない。しかしながら、施設に来ている
若者は多様な活動を通じて自信を培い、あり程度まで自発性に基づいた影響力をもっている
にも関わらず、このような発言,やデータがあるのは、おそらく現場レベルから国政レベル
への参加の「橋渡し」の難しさからであろう。それは必ずしも投票に限らず、政治家や政策
42
決定者に対して意思表示をする機会があるかどうかという指標も存在しているがそれでも、
国政レベルで参加の機会が欠如しているのは、ある意味では代表制民主主義の限界というこ
ともできる。そのような意味では国政への投票率を参加度合いの指標の比較対象にすること
はあまり有用ではない。またそもそも、代表性民主主義社会では影響力を行使できる人が限
定的になりうるという点も忘れてはならない。
また、スウェーデンでは国レベルよりも地域・地方自治多レベルの寿民の参加のコミット
メントのほうが高いことも、国政レベルへの参加が限定的になる理由に挙るだろう。分権
化が進んでいるスウェーデンの自治体は、国に次いでランスティング(県)、コミューン
(地方自治体)とあるが、コミューンへ支払われる税率は 31%(年間所得が 1 万クローノル
に達している場合)という高税を納めており、その使途の半分以上が社会福祉・教育に割り
当てられる。そして、コミューンの住民は、コミューン内の多くの施設を協同で所有し、サ
ービスに依存し、コミューンで行なわれる大半のことを政治家を選挙することによって決定
する。(川上,2005)故に、住民や市民にとって も重要なのは、身近な共同体であるコミ
ューンであり、重要なのはコミューンへの参加度合いであることがわかる。事実コミューン
への投票率は、2010 年には 18 歳以上の全世代では 81.%、うち 18-29 歳の若者層は 74.0%で
あり、グラフからも増加傾向にあるのがわかる。
一方で、自治体レベルにおけるスウェーデンの若手の政治家の数は、高投票率に反して
頭打ちである。スウェーデンの 18〜24 歳の若者は、地方自治体(コミューン)レベルでは
2006 年には 2184 人が候補者となり 329 人が選ばれている。(Ungdomsstyrelsen,2009)地
43
方自治体レベルにおける政治家の全体数は 2010 年時点では 12969 人14であるので、割合でい
うとわずか 2.5%程度15である。18 歳から 29 歳の年齢区分だとしてもわずか 7%にしか及ばな
い。県、国政レベルでは順にそれぞれ 6%,5%にしか及ばない。(LNU,2011)若者の影響
力を掲げるスウェーデンの若者政策は、ここに次の課題がみてとれるだろう。
結論
本稿では、スウェーデンにおける若者の社会参加について、主に余暇活動施設におけるそ
の実践について扱った。第一章では若者の社会参加の必要性と重要性について現代の若者が
社会的弱者・社会的排除の被害者に転落しているという状況認識を論じた。第二章では、子
ども・若者の社会参加とは何か、代表的であるロジャー・ハートの参加の梯子の枠組みにつ
いて批判検討をし、さらに児童の権利条約、EU 若者政策、スウェーデン若者政策、におい
て参加がどのように扱われているのかについて考察した。その際に、スウェーデンの若者政
策に特徴である、若者の社会的影響力と参加の関係性について論じた。第三章では、スウェ
ーデン首都ストックホルム南部に位置するあるユースセンターを事例にケーススタディを用
いて、ユースワーカーと利用者の若者のインタビューから、現場において若者の参加がどの
ようにして促されているのか、EU・子どもの権利条約・スウェーデン若者政策にそって参加
が促されているかどうか、そしてその課題について論じた。同章では、ケーススタディを実
施したスウェーデンの当該余暇活動施設における若者参加は、スウェーデン若者政策によっ
て導かれている方針に沿って現場レベルである程度実現されていると結論づけた。同時に、
余暇活動施設の利用者の若者層の変容、組織活動の結成数の減少等の余暇活動施設における
若者参加の課題と、地域レベルと国政レベルの若者の政治への参加度の相違や、高い投票率
に反する若年層の政治家の少なさなどの課題が、スウェーデンの若者参加の次なる課題とし
て指摘した。
14 スウェーデン統計局のウェブページを参照 http://www.scb.se/en_/Finding-statistics/Statistical-Database/TabellPresentation/?layout=tableViewLayout1&rxid=49b5a26b-b54c-4622-a0f6-1298a2a045c6 15 Youth today, 2009 の数字から筆者が独自に算出
44
おわりに
スウェーデンと日本を比較するということ
スウェーデンは福祉先進国として何かとよく引き合いに出され、福祉や環境政策などが
注目される。事実、多くのスタディツアーなどや著書が企画されては日本の方に利用されて
いる。フィンランドが PISA(国際的な学習到達度調査)でトップを占めるようになったこ
とが話題をよび、北欧という括りではありが、教育分野も注目されるようになった。結果と
して北欧礼参しすぎてしまうこともよく見受けられる議論だ。反対に、スウェーデンの
「闇」の現実を一面的に意図的に引用されることも多々ある。特に 近の傾向であるが、右
翼的な思想で移民等の受け入れを反対する人々が、ストックホルムで起きた若者の暴動等を
「移民政策の失敗」として引き合いに出しているが、それはあまりにも部分的であるし包括
的で学術的な議論を抜きにして語られることが少なくない。
そういった論調の中で必ず議論になるのが、「ではそれは日本にそのまま導入できるの
か?」という言説である。税制の仕組みや政治体制やイデオロギーの違いが根本的に違うの
で比較は参考にならないという論調だ。確かに、一面的で短絡的な北欧と日本の比較は現実
的ではない。スウェーデンの現地に足を運ばずに、二次情報をもとに形成された「北欧と日
本の比較」ほど現実的でないものはない。しかしその論調も度が過ぎると、「文化が違うか
ら」「国民性が違うから」として比較を諦めてしまう。
しかしだからといって、「まあ文化が違うからねえ…」というだけの理由で、北欧、スウ
ェーデンについて学び、比較を通じて日本の状況ひいては、スウェーデンの状況をよくして
いくことに貢献することを諦めるのには十分な理由とはならない。日本の子ども・若者をと
りまく社会の状況をよくするためのオルタナティブがあるのなら、どうしてそれを活用しな
いのだろうか。逆もまた然りである。
事実、社会科学において比較研究の起源については,アリストテレスの行った「ギリシ
ア都市国家憲法に関する比較研究」に求めている学者があるほど長い歴史を持っている
(2007,朴光駿)朴はこう続ける。
比較の意味についてドガンは次のように述べている「ある人間や観念,あるいは物
事を、他の人間や観念,物事と関係づけて評価することほど自然なことはなし。知
るためには基準となる目印が必要だからである。比較は も良質な理論を育む土壌
ともなりうる。それは社会科学が真に科学となりうるための手段でもある。デカル
卜の『われ思う,故にわれ在り』という言葉をもじっていえば,『われ比較す,故
にわれ思う』ということができるのであろう」(DoganandPelassy/桜井陽二訳,
45
1983:1-4。)
つまり、社会科学において異なる社会を比較して論じることは自然であり、社会問題の
解を導くのに適した方法だ。故に、スウェーデンと日本を比較することは可能であり、日本
の子ども・若者をとりまく社会的状況を向上させるだけでなく、スウェーデン社会にも示唆
を与える可能性があるということである。以上の認識の上に、筆者が 1 年半の欧州生活とこ
れまでの学びから「日本への示唆」を雑文ではあるが、試みる。また、本稿では扱いきれな
かったテーマ・課題について触れることで次回以降へと繋げれたらと思う。
日本への示唆
1. まず始めに、「若者と何か」という点である。日本では「若者」「青年」の定義が
明確ではなく、調査や管轄省庁によって大いに異なる。少年法では 20-29 歳、若年
者雇用の定義では、青年層に相当する 15-34 歳ごろ、社会組織である「日本青年会
議所」、「商工会青年部」は 20 歳-40 歳、「民主党青年局」は 40 歳以下の党員、「自
由民主党青年局」、「全国青年司法書士協議会」で 45 歳以下といった具合に統一され
ておらず、比較的中年も含んだ高めに定められている。欧州だとほとんどの国で、
若者政策を担当する省庁がありターゲットである若者の年齢を明確にしている。ス
ウェーデンだと 13-25 歳、EU では 15-25 歳として明確に記している。その範疇の中
で若者の「多様性」を認め、様々な若者の「見える化」を調査等で照らし出してい
る。
2. それに伴い、日本では若者政策が省庁・部門別であり非常に官僚的である点が次
に挙げられる。欧州では若者政策を担当する省庁がある。それは必ずしも、スウェ
ーデン青年事業庁のように一括して担当するケースばかりという訳ではなく、健全
育成分野のようなスポーツ部門や、高齢者・家族分野などに含まれて実施されてお
り、形態は様々である。これらは近年,EU が若者政策として力を入れてきた分野で
あり、国際連合や諸々の国際機関も若者向けの政策を打ち出していることによっ
て、若者分野でも法体系(legislation)と施策(Initiative)が明確になったことが若
者政策の出現を促進し、担当省庁や機関が明確になったのであろう。
3. 関連して、日本の行政組織体系はトップダウン・中央集権的であり、上が変われ
ばがらっと変わるが、慎重な検討するために時間を要する。ヨーロッパは分権的で
あり、連邦制を採用している国もあるがスウェーデンでも地方自治体(コミューン)
への権限委譲をし、国は調査研究を分担する等しているために「小回りが利く」印
象がある。
4. 日本の若者の生活のほとんどが、「学校教育」と「労働」にしめられており、「社
会参加」することが、「教育」と「労働」の分野に極端に偏っている。例えば、余暇
46
活動に対する参加すらも、学校の範疇で「部活動」に義務的に参加をさせられる。
また受験勉強へのプレッシャーもあり、部活をしていてもいなくても塾へ通い、「余
暇活動」を消費させる。ひるがえって欧州では、学校の「部活動」がほとんどな
い。体育館がない学校も多い。つまり学校が終わったら、家に帰るか地域のクラブ
活動に参加するしかないのである。ユースセンターへいくという選択肢も忘れては
ならない。労働に関しては、日本では「社会人」になることは「企業人」になるこ
とが一般的な認識として存在している事実が、このことを端的に示している。また
これは若者支援の分野でも顕著である。2000 年代から表出したニート・フリータ
ー・ひきもりなどの「社会的弱者」へと転落した若者への雇用支援がほぼ独占的に
「若者支援」となっている。こういった若者の職業的自立支援の取り組みを「ユー
スワーク」と呼ばれることがしばしばあるが、余暇活動や政治活動、市民活動への
参画という視点がこれらの取り組みの主軸におかれているとはいい難いだろう。
5. 一方で、政治参加の分野では、模擬選挙活動や政治家との対話の場の提供、など
が活発的になっているが、高校終了年齢の 18 歳から投票・被選挙権を保障しない限
り、根本的な解決策とはならないだろう。また、併せて政治教育・シティズンシッ
プ教育を通じて政治的リテラシーを座学と実践とを通じて民主主義について学ぶ機
会を提供しない限り、草の根の底上げは測れないだろう。さらに、スウェーデンが
若者政策の目標で「若者の実質的な影響力へのアクセスを保障すること」と掲げ、
若者が「お飾りな」参加者とならず、実際に若者の手によって社会への影響力を発
揮できているか検証し、実質的に保障していかない限り、政治家・行政による「子
ども・若者の声も聞いているよ」というパフォーマンスとして利用されるに留まる
であろう。
6. さらに 5 に関連して、日本では若者の傘組織・代表組織が欠落している。若者の
傘組織というのは、若年層全般を代表し、若者の声を地域・国政・学校運営へと届
ける組織である。スウェーデンでは、本章でも触れた若者会(Ungdomsråd)や、LSU
という会員として登録した全国の若者団体の声を代表し、青年事業庁や EU へのロビ
イングや意見交換をする団体、そして学校では生徒会が学校運営にできるだけ生徒
の声を反映することを目的に活動をしている。学校の運営や施設、さらには、教員
の採用までも実際に行なっている生徒会も中には存在している。(NPO 法人Rights,
2010)スウェーデンのみならず、英国でもイギリス若者国会(UKYouthParliament)
が若者意見を国政の場に伝えるための主要な役割を果たしている。日本でこのよう
な若者のいわば、「傘団体」が欠落しているのは、学生運動の時代の 1969 年に文科
省の初中局から高校生を政治に触れさせないようにしろと通達があり、以降若者は
社会から切り離され、勉強にのみ没頭することとなったという歴史的事実が影響し
47
ているとも言えるだろう。(広田,2010)
7. 社会教育、学校外教育分野でいうならば、「プレーパーク」や「遊び場」、年齢層
が若干下がるが、「児童館」などは日本にも存在し、場所や施設を子ども・若者に提
供して余暇活動の機会を提供している。学校教育における部活や受験勉強等が時間
を取っているために、ほとんど思春期層による利用は非常に限定的であるが、それ
でもそういった場所がないわけでなく、利用者もいる。しかし、利用者である子ど
も・若者の活動が「遊び」や「余暇活動」に限定的で、そこからその他の活動、例
えば、施設外における市民活動やボランティア活動などへと参画の幅を利かせてい
るだろうか。施設や遊び場に「始めから用意されてある」遊び道具・プログラムを
利用する「お客さん」に留まっていないだろうか。遊び場・施設というある意味日
常空間とはいい難い場以外の「社会」へ参加できる機会があるだろうか。
8. 後の示唆は、若者当事者の主体化を通じた参加の必要性である。若者支援、社会
教育の文脈におけるユースワークでは若者を支援及び教育の「対象者」そして対局
にある支援者・教育者・サービス提供者を専門家として位置づける。しかしこれは
度が過ぎると問題が生じる。パターナリスティックな支援ー非支援関係が明確化し
行き過ぎると、支援の「主体」ではなく「客体」となってしまい、支援者である
「専門家」や「サービス提供者」によって支援の必要性や知識についての判断を独
占され、不均衡な力関係に陥ることで、結果として支援対象者である「貧しい人」
や「若者」自体のエンパワメントが失敗に終わるということが様々な事例で起きて
いる。こうした事態に陥らないようにするために、当事者の主体化を通じ、「支援者
=専門家」というパラダイムを「被支援者=専門家」へとシフトさせ、支援・被支援
者の関係性を再構築することを若者分野でも行なっていくことの重要性が指摘され
ている。(津富、2011)これはスウェーデンの第三の都市マルメの移民郊外で地域統
合を促すエリアコーディネーターのフィオナが「人々のために(for the people)
から、人々とともに(withthepeople)へ、貧しい人々の『ために』でなく『とと
もに』。貧しい人々のこと『について』話し合うのではなく『とともに』」という方
針と合致している。そういった点で、筆者らが属していた YEC(若者エンパワメント
委員会)は、大学生による中高生参加活動の支援を行なってきたのだが、年齢がほぼ
変わらない大学生=若者当事者による支援ができていたように思う。経験もスキル
もないど素人の私たちでも中高生のサポートができたのはある意味、同じ若者とし
ての「専門性」を有していたからだろう。「若者とともに、若者によって、若者のた
めに」という価値観は YEC でも大切にしていた価値観であるが、その考え方は欧州
のそれと変わらない。事実、ユースワークは、「青少年分野における EU の協力につ
いての新たな枠組み(2010・2018)」16に関する欧州評議会決議において、以下のよ
16 The Council of the European Union (2009)
48
うに定義されている。
若者による、若者とともに行われる、若者のための、社会的・文化的・教
育的もしくは政治的な性質をもつ広範囲の活動を意味する広義の言葉であ
る。 近は一層、その活動に、若者のためのスポーツや支援が含まれるよ
うになっている。ユースワークは、特定の余暇活動ならびに「学校外」教
育の分野に属し、専門職あるいはボランティアのユースワーカーとユース
リーダーらによって運営され、ノンフォーマルな学習過程と自発的な参加
に基づいている
また、「専門職あるいはボランティアのユースワーカー・ユースリーダー」と上
述してあるようにユースワークは何も、専門職のみによって提供されるものでもな
いことがここから分かる。第一回欧州ユースワーク大会宣言では、ユースワークの
多様性を認め、専門職化に伴うボランティア活動などへの排外性の可能性への危惧
を示している。(CouncilofEurope,2011)日本においても若者支援の専門職化が
現在検討されている17が、これまでボランティアやインフォーマルな形で実施され
てきた多様なユースワークの経験を共有し、若者の一番の専門家である「若者」当
事者自身によるユースワークがより広がり、私たち若者自身の現在とそして未来が
心地よいものとなることを願う。
謝辞
本論文を執筆するにあたって多くの方にお世話になりました。大学 2 年から始めた YEC の
立ち上げに携わった当時の仲間たち、津富宏教授、関わった大人の方たち、中高生、これま
でと現在の YEC のメンバーたち、そして NPO 法人Rightsの活動で関わった方たち、スウェ
ーデン留学を後押しし、励ましてくださったみなさん、スウェーデンで出会った学生、教
授、インターンシップを受け入れインタビューにも協力していただいたユースセンターの職
員と若者、そして帰国後も暖かくご指導いただいたゼミの犬塚教授、そしていつも支えてく
れた家族に、心から感謝申し上げます。
後に、本論文提出締め切り日のちょうど一週間前に事故によりこの世を去った小学生
の頃からの幼なじみであり、ブレイクダンサーであり、私の人生の師匠でもある山本翔五く
んに、謹んで哀悼の意を表します。YEC の活動の原点となった長野県茅野市にある CHUKO ら
17 kaken.nii.ac.jp/pdf/2011/seika/C-19/14601/21530838seika.pdf
49
んど「チノチノ」は、中学の時からブレイクダンスを始めていた彼にとっても原点の場所で
ありました。先日の葬儀でも多くの同級生だけでなく、ダンスを教えていた高校生ら、チノ
チノの職員さんらも参列をしていました。彼のブレイクダンスに対する情熱、向上心、決し
て諦めず、粘っこく、妥協しないで頭を地面に何度でもこすりつけ続けてダンスの練習に励
んでいた姿はいつも僕にとっての励みになっており、いつも背中を押してくれました。僕だ
けじゃなくみんなが勇気づけられていました。ダンスだけではなく、音楽や趣味、お笑いも
全て山本くんから影響を受けた僕は育ってきました。いつでもあの笑いがまたできると安心
していたのが一番の後悔です。せめていなくなる前にまたお腹から笑いたかったです。もう
この世にはいないけれど、山本くんは僕の中で今でも、そしてこれからも鮮やかに生きてい
きます。山本くんの人生に関われたことが幸せでした。本当に心からありがとう。
50
参考文献
Arnstein, Sherry (1969): A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of
Planners, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216–224.
Bryman, A. (2008). Social research methods (3rd ed.). Oxford: Oxford university press.
Commission of the European communities. (2001) European Commission white paper - A new
impetus for European youth.
The Council of the European Union. (2009). “A Renewed Framework for EU Cooperation in the
Youth Field 2010-2018”.
The Council of the European Union. (2011) DECLARATION of THE 1ST EUROPEAN YOUTH WORK CONVENTION
European Commission 2001:16; Treaty of European Union, 1992: article 126; Treaty of European
Union, 2008: article 165) http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0681:FIN:EN:PDF
Gallagher, Michael. (2008). Foucault, power and participation. The International Journal of Children's
Rights, 16(3), 395-406.
Hart, Roger. (1997) Children’s Participation: The Theory and Practice of Involving Young Citizens in
Community Development and Environmental Care. London: Earthscan & UNICEF.
Japanese Youth Research Institute. (2009) The survey for junior high school and high school
student„s life style and conscious.
Kirby, P. with Bryson, S., Measuring The Magic? Evaluating and researching young people’s
participation in public decision making (London: Carnegie Young People’s Initiative, 2002).
Lansdown, G., “Criteria for the evaluation of children’s participation in programming”, Early Years
Matters 2004 (103), 35-39.
Lansdown, G., “International developments in children’s participation: lessons and challenges”, in
E.K.M. Tisdall, J.M. Davis, M. Hill and A. Prout (eds.), Children, Young People and Social Inclusion:
Participation for what? (Bristol: Policy Press, 2006).
Loncle, P., Muniglia, V., and Spanning, R. 2008. Introduction: Youth Participation in Europe ---
between social and political challenges and youth practice. In P. Loncle, and V. Muniglia, (eds.)
Youth Participation, Agency and Social Change: Thematic Report. UP2YOUTH.
51
Roberts, Helen, 2003. “Children’s participation in policy matters” in Prout, Alan – Hallett, Christine
(eds) Hearing the voices of children – Social policy for a new century. London: RutledgeFalmer
Susanna Brolin. (2011) DEMOKRATIKLAGET. Skärholmens sdf, Stockholm
The Association For Fair Elections. (2012)
http://www.akaruisenkyo.or.jp/070various/071various/377http://www1.odn.ne.jp/youth-
study/reserch/2009/tanjyun.pdf
UN.(1989) The UK Convention on the Rights of the Child. New york : United Nations.
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
Ungdomsstyrelsen. (2003) UNG 2003.
Ungdomsstyrelsen. (2008) Young people with attitude.
Ungdomsstyrelsen.(2009) The youth influence The Real Deal.
Ungdomsstyrelsen. (2010) YOUTH AND YOUTH POLICY- A Swedish Perspective.
Ungdomsstyrelsen. (2011) FOKUS 10.
Woodhead, M., & Montgomery, H. (2002). Understanding childhood: an interdisciplinary approach.
Wiley.
アーネ・リンドクウィスト, Lindquist, A., & ヤン・ウェステル Jan. (1997). Wester (著), 川上郁
夫 (訳) あなた自身の社会, スウェーデンの中学教科書.
岩田正美. (2008). 社会的排除: 参加の欠如・不確かな帰属. 有斐閣.
NPO 法人 Rights, 2010, スウェーデンスタディツアー報告書完全版
津富宏, 2011, 社会的排除の被排除者である若者の主体化を支える文脈形成に向けて
日本青少年研究所,2009, http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hyouka/part2/k_6/pdf/s2.pdf
広田照幸 「演題:子ども若者ビジョンから考える静岡の未来」『YEC わかもの白書』
YEC(若者エンパワメント委員会)、2010 年、33-38 項
平塚眞樹, 2006, 移行システム分解過程における脳欲観の転換と社会関係資本
宮本みち子. (2007). 格差社会と若者の未来. 同時代社.
朴光駿. (2007). 社会政策における比較研究の発展